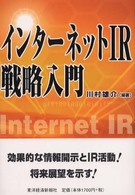内容説明
沖縄は歌にあふれた島である。雅な古典音楽や三線に彩られた島唄が今も歌いつがれ、新しいウチナー・ポップが続々と誕生する。なぜ、どこから、沖縄の歌は生まれてきたのか?500年にわたる島と音楽の歴史を、歌、人、エピソードなどで語る音楽読み物。三線音楽の神様・赤犬子。18世紀のスーパー・アイドル・吉屋鶴。戦前、沖縄音楽のレーベルをつくり自ら歌った普久原朝喜。戦後、コザを中心に活躍した嘉手苅林昌、照屋林助、登川誠仁など、きら星のようなスターの面々。世界的なヒット曲「花」の喜納昌吉。りんけんバンド、Cocco、安室奈美恵…。古典音楽からウチナー・ポップまで、沖縄の音楽のすべてがわかる決定本。
目次
第1章 歌と三線のスピリット(琉球古典音楽のヒーリング効果;古典のリズム、いにしえのビート;三線音楽の神様、赤犬子;尚真王と八重山のオヤケアカハチ;琉歌、サンパチロクの面白さ ほか)
第2章 われらウチナーンチュの歌(沖縄の武士、嘉手苅林昌に捧ぐ;明治のポップ・ミュージック「鳩間節」;ウチナーンチュの「民族大移動」始まる;チコンキー・フクバルの偉大なる革新;ゲット・アップ沖縄、ヒヤミカチ! ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
52
「何よりぼくらは、かの三味線まで、あっさりと捨ててしまっているではないか」(135pより)。語りかけるような読みやすさで、沖縄の音楽史がわかるエッセイ。沖縄について問いかけられている内容は重いが、音楽はそれもエネルギーにしてきたのだなと感じる。かつての宮廷音楽も民衆の音楽に合流して、今の音楽につながっている意味は大きいと思う。かえって本土の音楽は「伝統」を絶えず捨てながら今日まで来ているので、一貫した音楽史として語れるだろうか。紹介された曲で、実際に耳にしたものは少ないものの、ぜひ聴きたい曲がいくつも!2020/12/19
saladin
4
一見軽い読みものに思われるがさにあらず。2000年発行と少々古いが、そこに至るまでの古典音楽からウチナーポップまで、500年の沖縄音楽史が概観できる良書。後半の沖縄音楽ミニ事典も、”ミニ”とはなっているが充実しており、初心者には十二分に役に立つだろう。2023/03/04
Hiroki Nishizumi
1
参考になった。ただ上目線的な文章にちょっと馴染めなかったが。2023/11/08
ミー子
1
沖縄音楽について、500年前から現代までの歴史や人などを語った本。作者の沖縄音楽への愛が溢れている文章。沖縄音楽は、沖縄の風土と自然や、悲しみ、神々との交流とか、沖縄の心を歌った土着の音楽。そして、外から来た音楽と混ざって、新しく素晴らしい音楽が生まれること。そのような点はキューバ音楽やハワイの音楽など世界中の素晴らしい民族音楽も共通する。音楽はどんなジャンルであれ、奏でる人の心であり、それが人を感動させる。 本の後半は、沖縄音楽ミニ事典になっていて、読み物的なのは前半のみ。2018/10/02