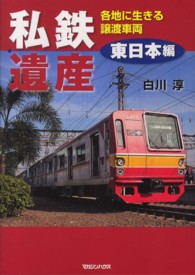- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
1986年、世界を震撼させたチェルノブイリ原子力発電所の爆発事故。近隣のベラルーシは、事故後も子どもたちの甲状線ガンが激増するなど、多大な被害をこうむった。そんなベラルーシ共和国の首都ミンスクの国立甲状線ガンセンターで、外国人としてただひとり治療にあたる日本人医師がいる。貧しい医療環境。不自由なことば。子どもたちの将来への不安。苦脳する被災地の人びととの対話…。とまどい、葛藤しながらも、希望をもって活動をつづける。地位や名誉をすて、医療現場の最前線に飛びこんだ医師がつづる、知られざるチェルノブイリの現実。
目次
1 決意
2 ベラルーシの医療現場
3 事故10年目の春
4 不思議の国ベラルーシ
5 外科医の日常
6 人々の闘い
7 希望
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
けんた
3
福島原発事故後の医療活動についても様々に提言されている現松本市長のベラルーシでの医療活動を記録したエッセイ。日本で報道されていることでは知ることの出来ない、汚染地域の日常を知ることが出来ました。誰も起こさない行動を自ら気負うことなく起こせる人は羨ましいし、自分もそうなりたいと思います。2011/05/25
kokekko
2
新潮文庫版を読了。ベラルーシにおける小児甲状腺ガンの治療に尽力した筆者の、ご当地での活躍をつづったエッセイ。チェルノブイリ事故の概説や放射能の影響について知りたいならば他の本のほうがよいかも。これは一人の医師がひとりの地球人として患者さんを助けた記録だ。おもしろいけれどちょっと鼻につくのは、ちまちまと入る「ベラルーシはこうだ。それに比べて日本の○○は~」というぼやき。せっかくベラルーシのある郡や町の実情を人間レベルで見てきた人なのだから、自分の故郷の有様だって「日本」と一くくりに語らなくてもいいだろうに。2011/07/05
くらーく
1
国の医療レベルと言うか、どれだけ医療費に回せるかが、大切だなと実感。日本では使い捨てているような道具が、繰り返し使われていたり、ろくな機材も無いところで、手術をしたり。 今の日本の医療費は、過剰だと思うけど、それはある意味幸せなんだろうな。2015/05/16
ottohseijin
1
「生きがい探しの旅」という言葉が象徴的かなあ。2011/08/20
-

- 和書
- 韓国語の基礎 〈2〉