感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽてちゅう
26
1979年2月初版。書庫の奥にあった本は長い時を経ても色あせず、未知の子育てを知らしめる。カナダの北西部で生活するヘヤー・インディアン。作者のフィールドワークを通じて語られるのは言わばカルチャーショック。ここでは子育ては親の仕事ではない。子どもの運命や将来はその子自身で切り開くもので、育て方によって決まるという考え方がない。親から「教わる」ではなく「自分で覚える」スタイルが子どもにも定着している。子どもが生まれながらにして持つ能力と可能性は計り知れない。では親に出来ることは何か?考えさせられる読書でした。2025/02/05
frosty
15
一番衝撃的だったのは、子どもに愛を注がない、むしろ邪魔に思う文化を持つ民族の人々がいるということでした。大学入学前の課題図書のようなものなのですが、確かに、言われないと手に取らないかもしれない、けれど、読み始めたら面白くて止まらない本でした。(面白いのは一概に私が子どもに興味があってかつ上橋菜穂子さんの影響で文化人類学に興味があったからかもしれませんが)なまじ小さいころに異文化体験をしてしまい、外国の教育とはこのようなものだ、という偏見を持ってしまっていた私にとってはものすごく衝撃的で、目からウロコでした2016/03/16
ひさだ
8
とある狩猟採集民族には教える・教えられるという概念がないそう。「誰に習ったの?」と聞くと、「自分で覚えたのさ」と返される。そこでは様々な大人の働きを見て、やってみることで自分のものにしていく。これって、流行りの教育法であるアクティブラーニングや、寿司職人の「見て覚えろ≒やって覚えろ」に近い気がする。体系化されたものを「教える」だけでは得られないものがあるのだろう。アクティブラーニングを前提とした小学校の「総合」の目標が、「変化の激しい知識基盤社会に対応する力を育てる」ことだというのは皮肉的で面白い。2019/06/14
たこらった
3
子どもは可能性に充ちている。それは環境に応じて開かれてゆく。開くか開かないかは本人の力次第だ。ヘヤー(hare)インディアンの4歳の幼女がひとり斧を振り上げて薪割りをする冒頭。他地域で得られた知見も搗き交ぜて静かに、だがラディカルに人間にとって学ぶとはどういうことか、その際の初期環境である家庭や地域共同体のエートスは文化によってどう違っているのかを考察。すぐ教わりたがる自分が情けなくなった←見て覚えろ。死ぬことの意味、死への態度についても反省させられた。血縁が極めて文化なのだということも。淡交は招福なり。2025/02/05
紺
3
実際に海外へ行って現地の暮らしを体験した著者が様々な家族のあり方を紹介・分析している。ヘヤー・インディアンなど聞きなれない民族の、やはり耳にしたことがないような文化の話は面白かった。欧米の文化でも日本では考えられないようなものはあるけど、ここで紹介される文化はその比じゃない。世界は広いなぁと改めて思った。2016/10/18
-
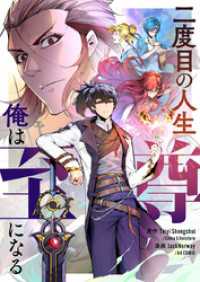
- 電子書籍
- 二度目の人生 俺は至尊になる【タテヨミ…
-
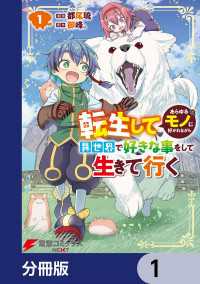
- 電子書籍
- 転生してあらゆるモノに好かれながら異世…






