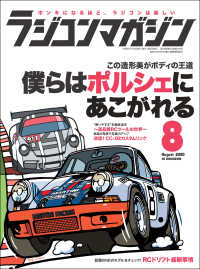内容説明
アリは不思議な生き物だ。人間と多くの共通点をもつ。高度に組織化され、寄生・里子・奴隷制まであるアリの社会。精緻な巣のしくみ。集団で餌集めをし、キノコを栽培し、アブラムシを牧畜する。コミュニケーションにはフェロモンと音を使う。そして驚くべき生殖のメカニズム…。アリを農業に利用する方法は?自然にやさしいアリの防除法は?無数の動植物と共存し、生態系を支えているアリの盛衰は、近年、自然破壊や公害汚染を示す「環境のバロメータ」としても注目されている。アリ学のABCから最新の知識まで。わたしたちの足もと、大地にくりひろげられる壮大なアリの宇宙へようこそ。
目次
1 アリとはどんな動物か
2 アリの社会
3 アリのふえかた
4 アリの食生活
5 アリの家
6 迷子にならない理由
7 アリのたたかい
8 寄生者と奴隷
9 アリの家のお客
10 アリと人間
著者等紹介
ノース,レイ[North,Ray]
ロンドン動物園に勤務後、ロンドン大学にてヤマアリの行動と生態の研究で博士号を取得。現在、サウサンプトン大学の研究員。王立昆虫学会会員。ハンプシャー州ロネジー在住。アリ研究の第一人者である
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
更紗蝦
9
「食うか食われるか」だけではない、蟻と他の生物(または蟻同士)の複雑な関係性には驚きました。ヤマアリには鉛やカドミウムなどの重金属が蓄積されるため、公害汚染の指標に利用できるという話も興味深かったです。人間のしでかした環境汚染という「罪」が、こうして(蟻自身はそれと知らず、何の利益もないままに)記録されているという事実は、蟻を通しての自然からの警告のように思えます。2015/01/20
saladin
0
今夏話題になったヒアリのことを知るために。本書は特にヒアリの記述に特化しているわけではないが、アリの生態がわかりやすく描かれており、専門知識がなくとも読み進められる。当初の目的とは違い、アリの驚くべき生態に感銘を受けることしきり。著者のアリに対する愛情が感じられ、こちらまで愛おしく思えてくる。考えてみれば、ヒアリが上陸したのも、経済のグローバル化に伴うもの。ヒアリ自身は生存本能に従ったまでだろう。が、だからと言って放っておけないのが、こうした”外来種”の問題なのだろう。2017/09/29