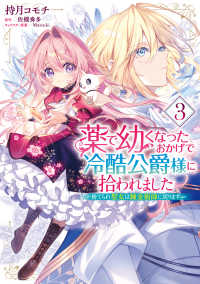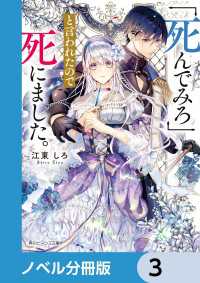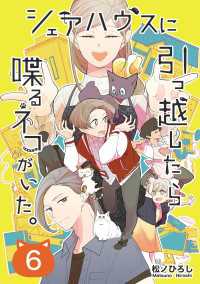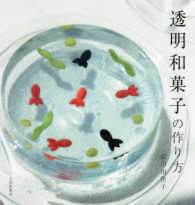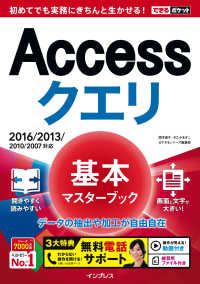出版社内容情報
生徒も教師も算数・数学が好きになる、「答えのない教室」の理論的・実践的ルーツがここに!
BTCの全貌がわかる決定版
本書は2023年刊『答えのない教室』のベースとなった本の邦訳である。著者は世界的な数学教育学者で、本書(原題Building Thinking Classrooms in Mathematics 2021年刊)はその代表作であり、一読すれば「答えのない、考える教室づくり」(以下BTCと略)のすべてがわかるようになっている。監訳者の梅木氏は六年以上にわたり、BTCを用いて年400回に及ぶ授業を実践するかたわら、開発者である著者のもとで算数・数学教育の研究を重ね、修士論文も書いており、BTCの国内最良の紹介者といえる。
日本での授業実践の様子は続編『答えのない教室パート2』(池田吉久著、2024年刊)でも紹介されているが、その特徴は際立っている。まずトランプを使って教室を三人ずつのグループに分ける(BTCでは対話を通じて考えるユニットとして三人が最適とされる)。次に机も椅子も片づけて広いスペースを作る。グループごとにホワイトボード一台とマーカーペン一本が支給される。生徒たちはボードの前に立ったまま思考をめぐらし、議論を交わす。そのあいだ教師は教室中を動き回って生徒たちの質問に答えたり、適宜ヒントを出したりする。その光景は通常の授業とはかけ離れている。しかしそれがいかに有効かは、生徒たちの生き生きした表情からおのずと明らかである。
本書では、著者が15年以上にわたる研究成果(400以上の教室、数千人の生徒へのインタビューなど)に基づいてこのメソッドを開発した経緯も語られる。つまり単なる実用書ではなく、確固たる裏づけのもとに「考える教室づくり」の有効性が示されているのである。
流山市立おおぐろの森中学校校長・前川秀幸氏は「答えのない教室」を、「にぎやかだけどうるさくない授業」と評した。その背景を含めた手法の全貌を、ぜひ日本の教育関係者のみなさんにも知ってもらい、生徒も教師も楽しめる授業づくりに役立てていただきたい。(編集部)
【目次】
目次
第1章 「考える教室」では、どのような課題を扱うのか
第2章 「考える教室」では、グループをどのように形成するのか
第3章 「考える教室」では、生徒はどこで授業を受けるのか
第4章 「考える教室」における机や椅子の配置
第5章 「考える教室」における質問への答え方
第6章 「考える教室」においては、いつ、どこで、どのように課題を与えるのか
第7章 「考える教室」における宿題の役割
第8章 「考える教室」で生徒の自律性を育むために
第9章 「考える教室」におけるヒントと発展課題の活用
第10章 「考える教師」における授業のまとめ方
第11章 「考える教室」における生徒のノートのとり方
第12章 「考える教室」において「評価」の対象として選ぶもの
第13章 「考える教室」における形成的評価の使い方
第14章 「考える教室」での評価方法
第15章 14の枠組みを結集して「考える教室」をつくる
著者等紹介
梅木卓也[ウメキタクヤ]
兵庫県加西市出身。2007年度のワーキングホリデーを機にカナダに渡り、学童保育や特別支援教育の支援員として教育現場に携わる。2019年度よりバンクーバー市の中高一貫校で数学教員を務めている。リリヤドール教授のもとで数学教育の修士課程修了。『答えのない教室』の著者であり、認定講師としても活動。コーチングや教育組織運営を通じてより良い教育環境の構築を目指し、カナダと日本で教員研修や教員養成に尽力
有澤和歌子[アリサワワカコ]
青山学院大学卒。阪急・阪神グループ、富士通、NTTグループなどでの勤務を経て「デンマーク株式会社」を設立。不登校の親子を支える「アナザーステージ」理事。47都道府県に、共創と世界平和を大切にした「公立風インター高校」の設立を目指して奮闘中。BTCの日本展開にも挑戦している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。