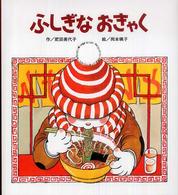目次
セクション1 選択する学びの目的とパワー(選択する学びの主要な効果)
セクション2 選択する学びの効果を高める方法(安心でサポーティブな環境をつくりだす;生徒のオウナーシップを強化する;生徒に学び方を教える)
セクション3 選択する学びの基本(よい選択肢をつくりだす;よい選択ができるように生徒をサポートする;生徒が選んだ活動を円滑に進める―すてきな学びをリードする;振り返りのパワー;教えるプロである教師の振り返り)
著者等紹介
エンダーソン,マイク[エンダーソン,マイク] [Anderson,Mike]
小学校の教師を15年間勤めたほか、幼稚園から大学院に至るまで教えた経験がある。現在は、教育コンサルタントやワークショップのファシリテーターとして活躍しており、「生徒に選択肢を提供する教え方」の普及をしている。7冊の著書がある。同じく教育者の奥さんと2人の子どもとともに、ニューハンプシャー州ダーラムに在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
奈良漬
1
メタ認知が大切。 またできた結果だけを褒めるのではなく、なぜうまくいったのか、というプロセスや工夫を褒めるようにする。2020/02/11
UP
1
「主体的な学び」を短期的には学習活動への集中、長期的には自ら学びを止めない人間になることだと定義すると、欠かせない要素は、学びのオーナーシップを高めること。そのための手段として「選ぶ」ことの重要性を学習のステップごとに整理した読みやすい1冊。吉田新一郎訳本は骨太な思想と実践が一体となった素晴らしいものが多い反面、現場への導入に多少時間もかかるものがあるが、これはすぐに導入できる。普段の授業のどこかに「選ぶ」学びを入れるヒント・視点をくれる。個人的にピンク・デシ両氏の理論とピアレビューのコツが参考になった。2019/07/18
アリョーシャ
0
ちょっと求めていたものとは違った。2022/03/13
にくきゅー
0
選択する→やってみる→振り返る というシンプルな流れ。選択するのは、言語活動だと読んだ。レポートであったり、新聞であったり、表現する方法を選ぶ。それらの選択肢が、指導目標の達成度を評価できるものであるかが留意点。また、選択の対象に学ぶ相手は入っていない。振り返るも様々ある。振り返りジャーナルもある。ペアで報告し合うのもある。また、タイミングも授業のはじめや終わり、単元のおわりなどある。目的に合わせて、しかし、必ず行うのが大事。おろそかにしてはいけない。2020/03/27
Ken.
0
「生徒が自立的な学び手になるために学び方を学ぶ必要がある (266)」これが(学習者が)選択する学びの最も大切な理由だという点は大いに頷ける。論理に飛躍があると思った方は是非ご一読を。「発達の最近接領域」や「成長マインドセット」など、教師必須の知見も優しく具体的に提示されている。実践者としての自分は、選択肢を提供するだけでなく、よい選択ができるように一人ひとりの学習者を支援する力量を鍛えていきたい。本書のどこにも言及はないが「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」の本質に迫るようなワクワクする内容でした。2020/02/12
-

- 電子書籍
- おじさん、この気持ちは何?【タテヨミ】…