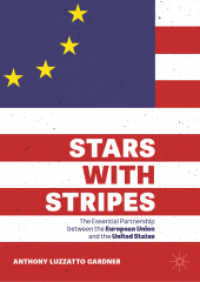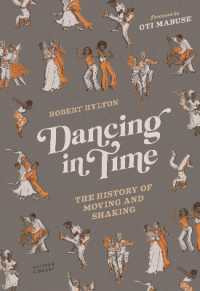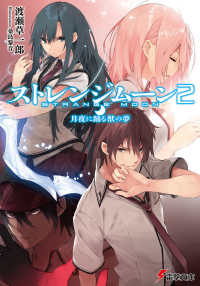出版社内容情報
★子どもが主体的な読み手として成長し、「本のある生活」を享受できるように導く画期的な授業とは?
読んでいる本があまりに面白くて、次の日に会った友人に、夢中でその本について語ってしまったことはないでしょうか? また、その友人が同じ本をすでに読んでいたことが分かり、自分とは全く違う読み方や解釈を聞いてびっくりしたり、新しい世界が開けたり、自分が抱いていた疑問が解決したという経験はないでしょうか?
本書には、子どもたちが「読むこと」を好きになり、主体的な読み手として成長できるような教え方が、具体的に描かれています。そしてその教え方は、前述のような、私たちが実際に本を読んでいるときに行っていること、起こっていること、そして本の内容やそこから広がる世界をより深く理解するのに役立つこと、といった経験と知恵に基づいています。
リーディング・ワークショップの行われている教室では、子どもたちは進んで本を読み、お互いに自分のお薦め本を紹介したり、自分たちで選んだ本をペアや小グループで読んで話し合ったりしながら、学び合っています。
そして教師は、読むことが人間に与えてくれる力を知っている「先輩の読み手」としてワークショップに関わります。子どもたちがしっかりと本の内容を理解して読んでいけるように、段階を追いながら、それぞれの子どもたちの必要に応じて、今よりも一段上のレベルで読めるように導いていきます。そして、子どもたちが本を読むことを楽しみながら、「本のある生活」をつくっていけるようにサポートします。
この教え方は、2007年に刊行された『ライティング・ワークショップ―「書く」ことが好きになる教え方・学び方』と共鳴しています。両方のワークショップとも、子どもたちが主体的な学び手になれるような教室をめざしていますが、『ライティング・ワークショップ』では「書くこと」を、本書では「読むこと」を軸にそれを描いているのです。
この本を参考にして、読むことが好きになり、読み手として成長し、卒業後もずっと「本のある生活」を豊かに送ることができる人を育てる授業を作り出していただけると嬉しいです。(こさか・あつこ 愛知大学法学部准教授/英語教育学・教育学)
内容説明
子どもたちは願っています、「本のある生活」が享受できることを。教室を舞台とした「読む」ことの物語。
目次
子どもたちと一緒に、楽しく読み書きを学べる場をつくる
世界を変える言葉―言葉のある教室
「読み聞かせ」と「考え聞かせ」
リーディング・ワークショップ
ミニ・レッスン
読み手へのコーチングとカンファランス
評価を授業に組み込む
「ガイド読み」と「効果的な読み」
話すことを読むことに活かす
年度当初のリーディング・ワークショップ〔ほか〕
著者等紹介
カルキンズ,ルーシー[カルキンズ,ルーシー][Calkins,Lucy]
もともとは小学校と高校の教師。1981年、コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ内に「読み書きプロジェクト」を創設し、所長を務めてきた。リーディング・ワークショップとライティング・ワークショップに関してよく読まれている著書を多数執筆。プロジェクトの活動の中心は、読み書きの分野で効果的な学び方・教え方を絶えず開発し、普及(=教員研修と執筆)すること
小坂敦子[コサカアツコ]
現在、愛知大学法学部准教授。大学卒業後は高校で英語を教え、アメリカの大学院に進学。学ぶことの楽しさに出会ったのは、アメリカ、バーモント州にあるスクール・フォー・インターナショナル・トレーニングでの大学院生時代。その後、ハワイ州にあるイースト・ウエスト・センターの奨学生として、同センターでの教員研修プロジェクトから多様な教え方を学習しつつ、ハワイ大学大学院教育学部で学び、博士号(Ph.D)取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mari
kaizen@名古屋de朝活読書会
kozawa
yoshimi750107
shizuca