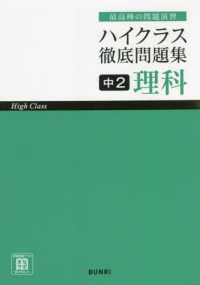出版社内容情報
■著作集刊行に寄せて
〈藤原保信著作集編集委員会〉代表 飯島昇藏
政治学者藤原保信教授が突然の不治の病に冒され、一年半の闘病の後に亡くなられたのは、一九九四年六月五日、五八歳の時であった。病床にあって藤原先生が最後まで問いかけ続けたのは、「現代における政治思想史研究の意義」であった。このたび没後一〇年という節目に合わせて、ここに著作集を刊行し、混迷の二一世紀に一層輝きを放つその思索の意義を世に問うものである。
著作集の第一の意義は、藤原先生の多岐にわたる著作を再編し、業績の全体を見渡しやすくすることによって、先生の研究を底流において貫いている問題関心の全貌を明らかにすることである。近代の秩序を規定してきた考え方を問題化し、原子論・機械論に代わる秩序のあり方を積極的に探ろうと試みた先生の思想の軌跡を辿ることを通じて、一九七〇年代から九〇年代にかけての思想状況において、「近代」に対してどのようなスタンスの取り方が可能であったかを、改めて理解することができると思う。先生は、アリストテレスの「プロネーシス(実践知)」やヘーゲルの「人倫」の概念などに着目しながら、常に実践哲学を復権することの必要性に注意を喚起し、政治学が、近代の秩序をどのような方向に再編していくべきかについての指針としての性格を取り戻すべきであると強調していた。
第二に、どれ一つとっても今なお色褪せない学問的意義をもったその個々のテクストを、著作集という形で改めて読者に供することができると考える。加えて〈公共性論〉など、これまでに公刊されていない論文も収録する(第一回配本・第一〇巻)。
藤原先生の著作には、ホッブズ論やヘーゲル論など、同時代の政治思想史研究の進展に貢献したものだけでなく、現代の政治理論・政治哲学に新しい学問的関心を喚起したものが少なくない。とりわけジョン・ロールズらの正義論、コミュニタリアニズム(共同体主義)、環境倫理学などについては、日本の政治学会においていち早く関心を寄せ、世に紹介した研究者の一人と言っても過言ではない。そうしたアクチュアリティを帯びた問題関心がどのように成立したか、またそれらが互いにどのように関連しているかを探り、藤原政治学の総合的把握を可能にすること。これが第三の意義と考える。
著作集刊行によって、ともすれば別個のものに別れがちな政治思想史研究と規範的な政治理論の研究とを、有機的に結びつけようとした一人の研究者の学問の姿をくっきりと浮かび上がらせることができると確信している。(いいじま・しょうぞう 早稲田大学政治経済学部)
ISBN4-7948-0651-5 ’05・1月刊
A5上製 三六〇頁 予五二五〇円
編集委員(アイウエオ順) 厚見恵一郎、梅森直之、荻原隆、押村高、金田耕一、川出良枝、岸本広司、齋藤純一、佐藤正志、添谷育志、田中智彦、谷喬夫、千葉眞、中金聡、引田隆也、松園伸、的射場敬一、谷澤正嗣、山岡龍一、山田正行
内容説明
「公」をとりもどす道、思想史から立ち現れる、有りうべき現代の公共性。没後10年。テキストの再編で甦る、藤原政治哲学の知の山脈。
目次
第1部 公/私概念の再検討(公共性の再構築に向けて―思想史の視座から;所有権論考 ほか)
第2部 近代市民社会の論理(ロックの契約論と革命権―『政府論』第一九章との関連において;科学・哲学革命と社会契約説―ホッブズを中心として ほか)
第3部 近代市民社会の克服(T.H.グリーンと社会主義;市民社会の止揚の論理をめぐって―ホッブズとヘーゲル ほか)
第4部 規範理論の再構築(『政治哲学の復権』をめぐって―添谷氏の批判に答えつつ;危機管理国家の正当性危機―政治理論の対応をめぐって ほか)
著者等紹介
藤原保信[フジハラヤスノブ]
1935年長野県生まれ。65年早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。元早稲田大学政治経済学部教授。政治学博士。政治思想史専攻。1969‐71年シカゴ大学、78‐79年オックスフォード大学に留学。日本政治学会、政治思想学会、日本イギリス哲学会などの理事を歴任。1994年没
斎藤純一[サイトウジュンイチ]
1958年生まれ。横浜国立大学経済学部教授を経て、早稲田大学政治経済学部教授。政治理論・公共哲学専攻
谷沢正嗣[ヤザワマサシ]
1967年生まれ。早稲田大学政治経済学部助教授。政治理論・現代リベラリズム専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
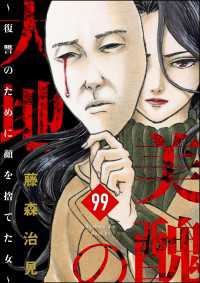
- 電子書籍
- 美醜の大地~復讐のために顔を捨てた女~…
-
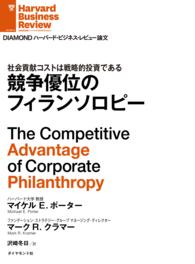
- 電子書籍
- 競争優位のフィランソロピー DIAMO…