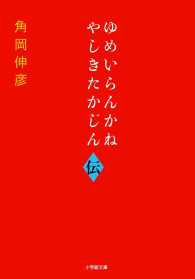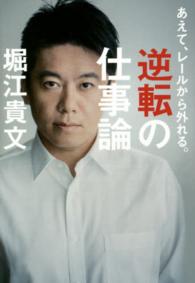内容説明
日本でも、一九九五年以降、「参加と共同」の学校づくりが全国に広がっています。この本では、そのパイオニア校からとして全国の学校から注目されてきた三校の取り組みを報告しています。高知県では一九九七年から土佐の教育改革の一貫として学校協議会が全県的に設置されて取り組まれてきましたが、その中で注目されてきた中学校が奈半利中学校です。東京大学教育学部附属中等教育学校は現在、三者協議会の実践と「学びの共同体」の実践で全国から注目されている中高一貫教育の学校です。長野県辰野高等学校は一九九七年から、三者協議会の実践とともにさらに地域住民の参加を加えた「フォーラム」の実践で全国の多くの学校のモデルになってきた学校です。この三校の一〇年にわたる「参加と共同」の学校づくりと授業改革の取り組みをまとめました。
目次
子どもたちは学校をつくる立場に立つ―奈半利中学校の共和制の学校づくり(「教えられる学習」から「つかみとる学習」へ;意見交流会は共和制の土壌づくり;子どもたちは学校をつくる立場に立つ;学級づくりと「共和制」―ある三年生の記録;気合いの入った「学P」について)
長野県辰野高等学校の「フォーラム」「三者協議会」と授業改善(地域住民とともに学校づくりを;生徒・父母の学校運営への参加;三者協議会と授業改善;参加と共同の学校が生みだすもの)
付録 戦後の学校運営への生徒参加の歴史と辰野高等学校の三者協議会―特別活動と生徒の参加・自治
東京大学教育学部附属中等教育学校の三者協議会と学校改革
解説 「私」と「三校」と「開かれた学校づくり」
著者等紹介
宮下与兵衛[ミヤシタヨヘエ]
前長野県辰野高等学校教諭(2008年3月まで)、長野県赤穂高等学校教諭(2008年4月から)
濱田郁夫[ハマダイクオ]
奈半利中学校教諭(2006年4月から休職。現在、安芸教職員組合専従)
草川剛人[クサカワタカト]
前東京大学教育学部附属中等教育学校副校長(2008年3月まで)、宝仙学園中学・高等学校女子部副校長(2008年4月から)
浦野東洋一[ウラノトヨカズ]
帝京大学教授(教育学科長、教職センター長)・東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
![[話売]性癖クラブ36 〈36巻〉](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1679765.jpg)
- 電子書籍
- [話売]性癖クラブ36 〈36巻〉
-
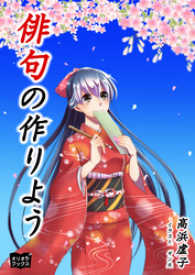
- 電子書籍
- 俳句の作りよう