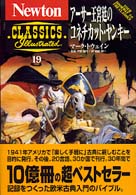内容説明
人道支援や開発援助は、誰の役に立っているのか?人助けと国益のはざまで揺れる「国際協力」の核心に迫る!
目次
第1章 国際協力のまなざし
第2章 国際協力の誕生
第3章 国際協力の表象
第4章 国際協力体験記を読む
第5章 国際協力の認識
第6章 援助批判・反批判を読む
第7章 国際協力の源流
第8章 開発の脱政治化を超えて
著者等紹介
北野収[キタノシュウ]
獨協大学外国語学部交流文化学科教授。専門は開発研究(国際開発、農業農村開発、NGO論)。コーネル大学で修士号と博士号を取得。企業で世論調査・市場調査に従事。農林水産省で農業経済事務官(国家1種)として、国際協力・ODA、農村整備・地域活性化、美しい村づくり、農業白書、行政改革会議等を担当。日本大学生物資源科学部准教授を経て現職。NPO法人環境保全修復機構(ERECON)理事、国際アジア食料研究所(IAFI)理事、スマート・テロワール協会顧問。日本国際地域開発学会奨励賞、日本NPO学会賞優秀賞、日本協同組合学会賞学術賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とある本棚
9
良書。本の主題は巷によくある「国際協力」の政治性を明らかにするものであるが、その手法として「国際協力」という言葉が日本で生まれた政治的背景、業界誌の途上国写真の変遷、そして国際協力の先達(拓殖学)の回顧録の読み解き、といった多角的な視点を持ち込んでいるのが面白い。流行りの「日本の開発協力の経験を途上国に」という動きの中に、ナショナリズムの芽を見ているのも興味深い。国際協力に関わる人はその政治性や権力性を自覚しつつ、グローバル化や国民国家の理論といった「大きな物語」に絡み取られないようにしなければならない。2022/07/09
Mealla0v0
5
国際協力は、その美名に反して実態としては国益に資する政策である。だが、そのこと時代が脱政治化されるのが開発の効果でもある。戦後日本において、開発援助は戦後賠償や資源確保のための経済協力として出発したが、国際協力の語は石油危機を背景に資源確保を目的としたJICA設立の際に生まれたが、その後自体は政治的無臭として受け取られていった。だが、この空隙に開発ナショナリズムは充満していく。途上国のニーズに反した先進国のニーズ規定、開発研究における日本ブランドの強調などである。2023/06/24
-

- 和書
- グレタ・ガルボの眼