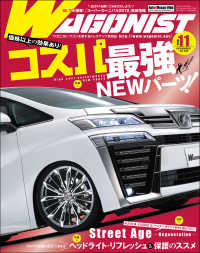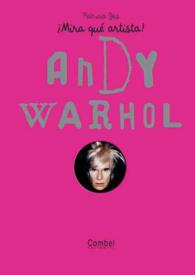出版社内容情報
労働の機械化が現実のものになりつつある現在。AIが導入されたリアルな未来を見据え、実際の企業の現場への取材等を通して、具体的な人間とAIの関係を提言する。労働の機械化を恐れることなく、また人間自身が「機械化」することもなく、人間らしさを失わずに働く未来のための啓蒙書。
「ロボットが世界を破滅させるなら、それは私たち自身が生み出した結果なのだ。テクノロジーによる革命のおかげで世界がもっと公平で幸福で豊かな場所になるのなら、それは私たちが果てしなく理屈をこねたり議論を続けたりするのをやめて、自らの運命を制し、未来に備えることができたからに違いない。」(本書より)
<目次より>
[第1部 機械 ]
第1章 サブオプティミストの誕生
第2章 ロボットに奪われない仕事という神話
第3章 実際にはどのように機械が仕事を奪うのか
第4章 上司はアルゴリズム
第5章 凡庸なボットに注意せよ
[第2部 ルール]
ルール1 意外性、社会性、稀少性をもつ
ルール2 機械まかせに抗う
ルール3 デバイスの地位を下げる
ルール4 痕跡を残す
ルール5 エンドポイントにならない
ルール6 AIをチンパンジーの群れのように扱う
ルール7 ビッグネットとスモールウェブを用意する
ルール8 機械時代の人間性を理解する
ルール9 反逆者を武装する
内容説明
人工知能が上司になったら、あなたはどうする?労働の機械化が実現しつあるいま、あるべき人間とAIの関係を、トヨタやUberなどの事例から得た考察を通して提案。機械時代に人間らしさを失わずに働き続けるための指南書。
目次
第1部 機械(サブオプティミストの誕生;ロボットに奪われない仕事という神話;実際にはどのように機械が仕事を奪うのか;上司はアルゴリズム;凡庸なボットに注意せよ)
第2部 ルール(意外性、社会性、稀少性をもつ;機械まかせに抗う;デバイスの地位を下げる;痕跡を残す;エンドポイントにならない ほか)
著者等紹介
ルース,ケビン[ルース,ケビン] [Roose,Kevin]
『ニューヨーク・タイムズ』紙のテクノロジー担当コラムニスト。ポッドキャスト番組『ラビットホール』でホストを務め、『ザ・デイリー』にもレギュラーゲストとして出演している。自動化とAI、ソーシャルメディア、偽情報とサイバーセキュリティー、デジタルウェルネスなどについて執筆とメディア出演により発信している。『ニューヨーク』誌の記者、テクノロジーを扱うTVドキュメンタリーシリーズ『リアル・フューチャー』の共同エグゼクティブプロデューサーの経験もある。2冊の著書「Young Money」と「The Unlikely Disciple」が『ニューヨーク・タイムズ』のベストセラーリスト入りしている。カリフォルニア州オークランド在住
田沢恭子[タザワキョウコ]
翻訳家。お茶の水女子大学大学院人文科学研究科英文学専攻修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やましん
pinevillageKNG
Humbaba
namtek
古民家でスローライフ