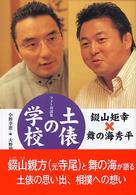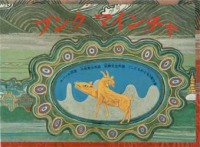出版社内容情報
大正から昭和にかけて活躍し、最後の幇間と言われた著者がヨイショのしか
たから接客術、遊びの極意、珍芸裏芸までを綴った抱腹絶倒の自伝エッセイ。
【著者紹介】
1907年浅草生まれ。最後の幇間といわれ大正から平成のはじめまで活躍。後進の指導も行い悠玄亭門下に数人の弟子を育てた。
内容説明
花柳界50年の玉介師匠が語った、たいこもち人生とお座敷哲学。江戸のお大尽たちのお座敷遊びを盛り立てた、名物幇間の洒脱な生き様。
目次
1 浅草旧見たいこもちの世界(たいこもちは遊びの番頭;はじめて出たのが、浅草旧見 ほか)
2 芝居好きから芸人に(おやじは酒屋で道楽者;子供のころから芝居に夢中 ほか)
3 たいこもちのお座敷哲学(相手の目を見てお辞儀する;たいこもちは「芸」より「間」 ほか)
4 時代は変わる、遊びも変わる(「臨検」「臨検」で座は白け;国賊もので、スイマセン ほか)
終わりに 今の遊びは、なってない(今の宴会にゃスキがないんだ;社用族に本当の遊びはできないよ ほか)
著者等紹介
悠玄亭玉介[ユウゲンテイタマスケ]
本名・直井巌。明治40年(1907年)、東京浅草の酒屋の息子として生まれる。生来の芝居好きが高じ、三好家松好の名で、歌舞伎声色の芸人になる。昭和2年(1927年)桂小文治師に入門、桂小祐の名で落語家に。昭和4年(1929年)五代目三升家小勝師の弟子になり、三升家勝好として二ツ目に。また、常磐津岸沢式佐師のもとで修業して岸沢式吾太夫の名を許され、さらに日本舞踊七世坂東三津五郎師門下で直門坂東三津介を襲名、師範となる。昭和10年(1935年)浅草旧見より桜川玉七師の家から、桜川玉介として幇間人生に入る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
ショ
Kazuo Ebihara



![無敵の地方公務員[上級]過去問クリア問題集 〈‘19年度版〉](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44714/447146003X.jpg)