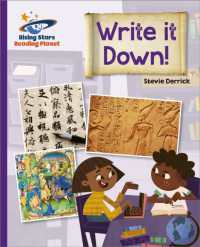出版社内容情報
「昔話には、なぜ老人が多く登場するのか?」という素朴な疑問を出発点に、全国に残る6万話もの昔話から、古典文学までを徹底分析。昔の老人の知られざる生態が明らかに! 超高齢化社会の今、老齢世代も、これから老人になる人も、古典文学や昔話、民俗学、昔の日本人の歴史・暮らしに興味のある人も、必読。前著『本当はひどかった昔の日本』が話題をよんだ、古典エッセイストの著者が初挑戦した異色の老人論!!
● 昔話に登場する「老人」とは一体何歳くらいか?
● 桃太郎は、爺婆が桃の汁を吸って若返り、交わった結果、誕生!
● 浦島太郎が竜宮城に行った本当の目的は、姫との「性愛」!
● 古典文学には70過ぎの「婚活老人」が頻出!そのわけは?
● 律令が定めた古代の定年は70歳!
● 平安時代の老人は、自傷行為で「極楽往生」をめざした!
● 平安時代は、女は40過ぎてもまだ若い!江戸時代は30でババア扱い!
● なぜ鬼爺とは言わず、「鬼婆」と言うのか?
●「 姥捨て伝説」は本当の話なのか? ……などなど
【著者紹介】
横浜市生まれ。古典エッセイスト。早稲田大学第一文学部卒。個人全訳『源氏物語』全六巻、『源氏の男はみんなサイテー』『ブス論』『愛とまぐはひの古事記』(以上、ちくま文庫)、『快楽でよみとく古典文学』(小学館)、『本当はひどかった昔の日本』(新潮社)など著書多数。
内容説明
昔の老人はやばかった!七十過ぎても“婚活”!姥捨て山に捨てられても、みごと生還!極楽往生したくて、井戸にダイブ!『舌切り雀』『浦島太郎』『源氏物語』…などの昔話や古典文学に描かれた「老人像」を追い、「昔の老人の知られざる生態」に迫るユニークな本!
目次
昔の老人の人生―昔話と古典文学が伝える貧しさや孤独という「現実」
昔話の老人は、なぜ働き者なのか―「爺は山で柴刈り、婆は川で洗濯」の背景
昔話の老人は、なぜ「子がいない」のか―「わらしべ長者」のルーツを探る
家族の中の老人の孤独―「姥捨て山」説話と「舌切り雀」の真実
古典文学の中の「婚活じじい」と「零落ばばあ」―平安・鎌倉期の結婚事情
昔話に隠された性―「浦島太郎」が竜宮城に行った本当の理由
古典文学の老いらくの恋と性―『万葉集』から『東海道中膝栗毛』まで
古典文学の中の「同性愛」の老人たち―爺と稚児、婆と美女の物語
昔話は犯罪だらけ―老人たちの被害と加害
自殺や自傷行為で「極楽往生」?―昔話の往生話と平安老人たちの「終活」
老いは醜い―昔話の「姥皮」と大古典の老人観
閉塞状況を打開する老人パワー―古典文学の名脇役たちと、棄老伝説
「社会のお荷物」が力を発揮する時―昔話はなぜ老人が主役なのか
昔話ではなぜ「良い爺」の隣に「悪い爺」がいるのか―老人の二面性と物語性
昔話はなぜ語り継がれるのか―『源氏物語』の明石の入道・尼君夫妻が子孫に伝えたこと
昔話と古典文学にみる「アンチエイジング」―若返りの目的はさまざま
実在したイカす老人―成尋阿闍梨母、乙前、世阿弥、上田秋成、四世鶴屋南北、葛飾北斎、阿栄
著者等紹介
大塚ひかり[オオツカヒカリ]
1961年横浜市生まれ。古典エッセイスト。早稲田大学第一文学部日本史学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小梅
AICHAN
ユウユウ
tomi
ロマンチッカーnao
-

- 和書
- 沖縄を撃つ! 集英社新書