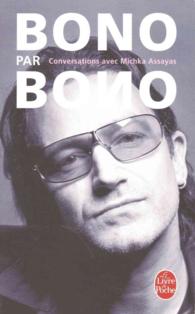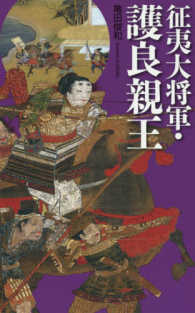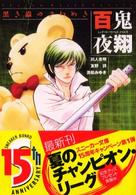- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
八女、土佐、出雲、黒谷、美濃、越前、加賀、越後小国…今、紙里はどうなっているのか、そしてどうなっていくのか?「手すきと機械すきはどう違うのか」「手すき和紙の材料、作り方」など手すき和紙の疑問に答えるとともに、日本の原風景ともいえる全国各地の「紙里」を訪ねる。
目次
1章 今、紙里に何が起きているのか?
2章 江戸・京都・大坂を支えた紙里
3章 紙祖神たちの里
4章 僧が興した紙里
5章 古代・中世より伝わる歴史の紙里
6章 落人が開いた紙里
7章 殿様が奨励した紙里
8章 幕末・明治~昭和期に注目を浴びた紙里
9章 一代漉きの挑戦
エピローグ 日本の原風景を残す紙里
著者等紹介
菊地正浩[キクチマサヒロ]
旅ジャーナリスト。昭和14年東京両国出身。専修大学法学部卒業。三井銀行(現三井住友銀行)支店長、(株)ゼンリン、日地出版(株)の役員などを経て、現在、(有)ケイエスケイ(菊地総合企画)を運営する。日本国際地図学会、旅ジャーナリスト会議、特定非営利活動法人「日本トイレ研究所」、国際ロータリー「蕨ロータリークラブ」などに所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
4
福井の越前和紙は興味深い(56頁~)。1500年の歴史が偉大に思える。紙能舞で子供が紙漉き唄を歌う神事があるという。昨夏猛暑で避暑に行ってたとこもそうだったが、良質の紙はこころ落ち着く小さな川の清浄な水から出来上がるということから、人間のこころも汚い川や汚染水タンクとか言っているところでは汚染されてしまうのであろう。今こそ、伝統的な紙づくりと3.11以来の汚染水タンクは全くの対極にありながらも、同じ日本列島に共存しているという実態を重く見るべき時に来ている。2013/03/13
MatsuNoHon
1
こんなにも伝承が途切れているものか、と軽いめまいがする。 農家が、冬の副収入として漉くようになった和紙。洋紙の生産性向上や清流が失われたこと、稼ぎが小さくなってしまったことにより衰退を辿っている和紙。 和紙が伝承されていた土地の歴史や、復活させた方の紹介、一代漉き師として全国で活動を続けている方々を紹介している。 きっと風景が素晴らしい、住みにくい土地がたくさんあるのだろう。訪れてみたいなー。2018/11/30
メルセ・ひすい
1
生活必需品の和紙は清冽な清流の流れがあれば全国どこでも漉かれていた。歌舞伎も落語、相撲、★書道、茶道、…便箋 封筒 葉書 扇子 団扇 紙衣カミコも江戸期には常用されていた。 原料の繊維は 楮コウゾ 三俣 桑 杉 松 竹 笹 蕗 バナナの葉 芭蕉 繋ぎの糊には米糊 蒟蒻 蕨 彼岸花 菫 水仙 トロロ葵 糊空木 を利用する。 日本の文化は和紙の文化である。しかし今、紙里では様々な問題が浮上している。手漉き和紙をこよなく愛す旅ジャーナリストが、東日本大震災をはさんで、日本列島の紙里をくまなく探訪した旅の記録。2012/12/07
こんぺいとう
0
和紙の里を訪ねて、全国津々浦々著者が飛び回る貴重なインタビュー書籍。 これを読んで、和紙が作られるまでの過程の細やかさ、丁寧さ、素晴らしさを知る。 おめでとう、重要無形文化財「和紙」。