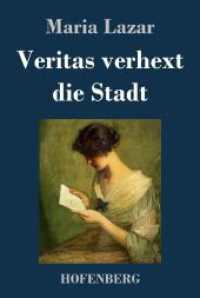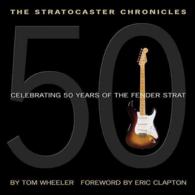出版社内容情報
樹齢千年以上の巨木が林立する驚異の島、屋久島。本書の著者は、重機の入らない峻険なこの島の山で、人力で巨木を掘り起こし運び出すなど、半世紀以上にわたって山に生き、木を守りつづけてきた。少年時代からあらゆる技術の移り変わりに立ち会い、無数の巨木に触れてきたなかで培われたその技術は圧倒的なものだ。千年、山を守るとは?山に残された文化とは?失われゆく伝統の「技」の最後の継承者が、その生涯と仕事を語る。
内容説明
樹齢千年以上の巨木に覆われた島、屋久島。重機の入らない峻険なこの島の山で、巨木を倒し人力で運び出す「山守」の仕事。その視線は、千年先の山の姿を見つめている。少年時代からあらゆる技術の移り変わりに立ち会い、無数の巨木に触れてきたなかで培われたその技術、知恵とは―。失われゆく伝統の「技」の継承者が、その生涯と仕事を語る。
目次
第1章 山の仕事に出合う
第2章 巨木を動かす
第3章 失われゆく技
第4章 山の中で生きる
第5章 千年、山を守る
第6章 最後の仕事
著者等紹介
高田久夫[タカダヒサオ]
昭和9(1934)年、鹿児島県屋久島生まれ。十七歳から山で働き、大径木の伐採、搬出、土埋木の伐り出しなど、さまざまな山仕事を経験。かつての屋久島の山仕事の実際を知る数少ない一人。いまも若者を指導し、屋久島の森の復元を目指して苗木を植えつづけている。有限会社「愛林」代表
塩野米松[シオノヨネマツ]
昭和22(1947)年、秋田県角館町生まれ。作家として活躍する一方、職人の聞き書きを精力的におこなう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
布遊
TATA
ゆうゆう
Makoto Yamamoto
-
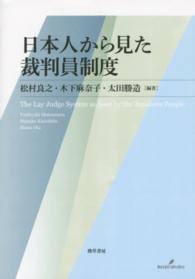
- 和書
- 日本人から見た裁判員制度