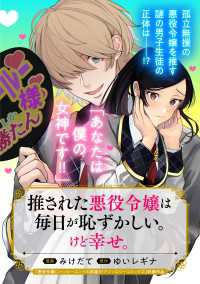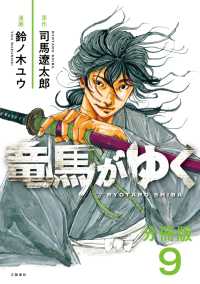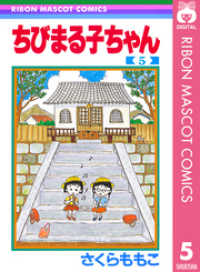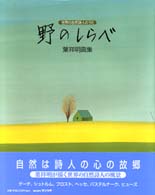出版社内容情報
亡命者らの証言をもとに政治犯の家族を三代にわたり拘禁する「管理所」をはじめとする収容所の全貌を明かした衝撃のレポート。
内容説明
カンボジア、ルワンダにおける集団殺害を調査・検証してきたデビッド・ホーク氏と東アジア専門家からなる北朝鮮人権アメリカ委員会が、24人の元収監者への聞き取りをもとにまとめた人権報告書である。「管理所」と呼ばれる政治犯収容所から、中国当局によって強制送還された脱北者を収容する拘留施設にいたるまで、36カ所を特定。いずれの施設でも収監者にわずかな食糧しか与えずに重労働を課し、恒常的に暴力がふるわれ、死亡率がきわめて高く、ときに拷問や人種的嬰児殺しがおこなわれる実態が生々しく描き出されている。独裁体制維持の要として、金日成・金正日父子が徹底的に隠しつづけてきた収容所の全貌を初めて明るみに出した決定的と言うべきレポート。7カ所の収容施設を撮影した衛星写真31点を収録。
目次
1 「管理所」「教化所」―粛清された人びとの収容施設とその処遇(「管理所」―政治的懲罰労働集落;「教化所」―長期にわたって収容し、労働を科す施設)
2 「道集結所」「労働鍛錬隊」―拘留施設と中国から強制送還された人びとの処罰(短い監禁、高い死亡率;最悪の出来事―嬰児殺し、強制堕胎)
3 拷問、嬰児殺し―証言から得られた拷問と嬰児殺しに関する情報(拷問についてのまとめ;人種的嬰児殺しについてのまとめ)
4 人権状況改善勧告―北朝鮮および関係各国に対する勧告(朝鮮民主主義人民共和国に対する勧告;中華人民共和国に対して ほか)
付録
著者等紹介
ホーク,デビッド[ホーク,デビッド][Hawk,David]
アメリカのアムネスティ・インターナショナル前理事。ヒューマンライツ・ウオッチ・アジア顧問。1980年代初めから半ばにかけて、クメール・ルージュの集団殺害を調査・分析。その後、ニューヨークにカンボジア文書調査委員会を設立。95年、ルワンダの集団殺害を調査。96年~97年、国連人権高等弁務官カンボジア事務所監督として国連に勤務。2001年~03年、ブランダイス大学で人権、調停及び国際法に関する特別研究員
小川晴久[オガワハルヒサ]
東京大学名誉教授・二松学舎大学特任教授。「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」名誉共同代表。1941年愛知県生まれ。63年東京大学文学部(東洋史)卒業。72年東京女子大学専任講師、80年東京大学教養学部助教授、89年同教授を経て現在にいたる
依藤朝子[ヨリフジトモコ]
1974年生まれ。青山学院大学文学部卒業。早稲田大学修士課程修了(西洋史)。オレゴン州立大学で米国政治、現代史、イエール大学大学院で米国政治、社会、現代国際関係、韓国延世大学で韓国語を学ぶ。「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
ふじこ
me
かじ