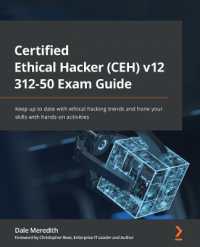内容説明
いくら考えてもいいアイデアが浮かばない。どこかにいい情報かヒントでもと、ついインターネットで検索していまう人も多いだろう。ところが過剰な情報は、かえってひらめきを阻害するという。もちろん、ただ考えていてもだめだ。画期的なブレークスルーに至るには、それなりのプロセスがある。コンピュータには真似のできない人間固有の「考える力」を駆使して、頭の中に眠るひらめきを呼び覚ますにはどうすればいいか。一段上の知の高みに上るための道案内。
目次
序章 「考える」とは何か―散歩のすすめ
第1章 ひらめきの見つけ方―ひらめきのプロセスを知る
第2章 考えつづける技術―「わかる」という誤解
第3章 夜の歌―ひらめきはいつ訪れるか
第4章 Mind of Blue―脳を忘れる
第5章 ひらめきを阻害するもの―情報糖尿病とつきあう
終章 人間は何を知ることができないか―「考える」ための三つの問い
著者等紹介
吉永良正[ヨシナガヨシマサ]
1953年、長崎県生まれ。75年、京都大学理学部(数学専攻)卒。77年、同大学文学部哲学科卒。大東文化大学文学部助教授。出版社勤務を経てフリーランスのサイエンス・ライター。91年、講談社出版文化賞科学出版賞受賞。2004年4月から現職
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿呆った(旧・ことうら)
1
養老孟司にも通じるが「自然」の必要性を論じている。単に森林やエコという意味ではなく、人間も自然そのものだということだ。例えば睡眠は無駄でなく必要である。 養老さんの言葉の「脳化」、吉永さんの「わかったと思い込む頭の固さ」は科学という名の独断で、人間はああすればこうなると単純にはいかない。吉永さんは科学論(複雑系等)を、養老さんは解剖を専門にしており、一見科学の申し子のような方々が科学の独断を否定し「自然」というキーワードで人間を見直している。納得させられるだけの根拠もあった。私にとって有意義な一冊だ。2015/02/21
-

- 電子書籍
- 【単話売】熱愛プリンス お兄ちゃんはキ…