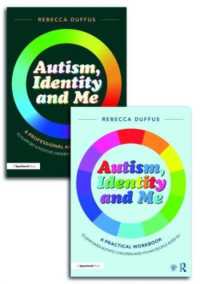出版社内容情報
「生まれつき」は存在するか?
哲学史上もっとも危険かつ複雑な論争のゆくえ
人間の合理的な営みの根源を成す、知能や言語能力、推論や数学の知識は、生まれつきのものなのか、それとも環境によって書き込まれたものなのか。複雑かつ神秘的な人間の心の仕組みをめぐって、ときに政治や道徳を巻き込みながら激しく交わされた論争の歴史を丁寧に解きほぐし、「人間本性」という哲学史上の壮大な謎に迫る、俊英による挑戦の書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
15
かりに人間の本性=「合理性」だとすると、その基盤となる知能・言語・数学はどのように成立したのか?。なんらかの目的とか効用とかラグランジアンが明確に定義されていて、その最適化プロセスを法則と呼ぶのであれば、京極堂のように「この世には不思議な事など何もないのだよ」と言い切ることができる。逆にいうと不合理に見えることがあるとしたら、法則(最適化プロセス)が間違っているのではなく、最初に設定した目的とか効用が現実に即していないのだろうと推測される。2022/01/14
愛楊
3
最も著者の専門に近くBoghossianやWilliamsonの議論のサーベイとなっている最後のアプリオリの知識に関する章が最も良かった。日本語で読めるのはありがたい。2025/05/08
Go Extreme
2
人間本性の科学史―ダーウィンからディープラーニングまで: ダーウィンの進化理論 猛威をふるった優生学 環境の影響を重視する思想 生得主義と遺伝仮説の復権 経験主義への福音ーニューラルネット研究 イデオロギーにどこまで中立を保てるか 知能―遺伝か環境かそれとも: 知能研究 量的遺伝学 知能の遺伝・環境構造 人種とIQ フリン効果 言語―文法能力は本能か習慣か: 生得主義の主張 刺激の貧困論法 言語の起源を求めて 数学―アプリオリな知識はいかにして可能か、あるいは不可能か: 認識論 合理主義の伝統 規約主義2021/10/25
borisbear
1
4章「数学 アプリオリな知識はいかにして可能か」に特に興味を持って読んだ。まず知識の標準的定義を提示し、その第三要件「正当化」が数学の知識でどう実現しているか問うという展開で、本書ではその答えの例として「規約による」「意味理解による」「経験的に検証される信念体系全体の一部であることによる」などが紹介される。全体的に議論がよく整理されているのは素晴らしい。ただ私自身はこのような、例えば「7+5=12がなぜ正しいと分かるのか」という問題提起の仕方は、哲学にありがちな悪い誘導ではないかと思う。2021/11/21