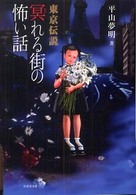内容説明
燃えあがる情熱と醒めた知性と―太郎が唱えた「対極主義」は彼の生きかたそのものだった。初の本格的岡本太郎論。
目次
顔のなかの「黒い穴」
お笑いか教祖か前衛か
バタイユと「爆発」
対極主義と「絶対的な引き裂き」
「コジェーヴの日本」への挑戦
縄文的なるものと日本的なるもの
日本と日本列島の果てしない相克
「森の掟」とギャグ漫画
岡本太郎とタイガー立石
「太陽の塔」の皮膜を裏返す
見えない都市とベラボーな塔
一九七〇年の祭りの理論
なんにもない世界
著者等紹介
椹木野衣[サワラギノイ]
1962年、秩父市に生まれる。同志社大学文学部卒業後、90年代初頭より美術評論家として活動を始める。現在、多摩美術大学助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
28
晩年にTVで芸能人として消費された「芸術は、爆発だ!」を、1936年永住を決意したパリで実際に交流のあったバタイユの思想から肯定的に読み替えます。「進歩や発展といった近代の幻想から解き放たれたわれわれわれの生命が、一気に解放され変容する、その醒めた歓喜の瞬間を捉えた言葉なのだ。」単に歴史を継承しない反ヘーゲルということではなく、バタイユがそうであるようにヘーゲルから自己否定である「否!」という響きをコジェーヴを補助線にして引き出し、死を賭けても危うい選択に身をさらすべきだという太郎の信条の起源に迫ります。2021/01/13
kaz
3
久しぶりに岡本太郎関連の本を読んだ。面白くて数時間で読み切ってしまった。岡本太郎の墓の像に秘められた空虚な黒い穴の謎、矛盾に引き裂かれた顔の謎から始まり、バタイユやマルセルモースからの影響、縄文の発見、父、一平の漫画からの影響、そして大阪万博での太陽の塔と祭りについての考察、最後に明日の神話から、再びあの空虚な黒い穴へと戻ってくる構成は見事。「黒い太陽に、矢をはなとう。そして赤いカニをしとめなければならない。」社会が絶望に彩られた時は芸術で彩らなければならない。今度東京に行ったら岡本家の墓に行ってみたい。2020/11/02
ルンブマ
2
椹木野衣は岡本がバタイユの発足した社会学研究会や秘密結社「アセファル」に参加していたという事実関係から、岡本の〈対極主義〉の概念は岡本がパリに留学していた時代にバタイユを通したヘーゲル理解に基づいて形成されたと推察したが、椹木の推察に異議を唱える日本の美術史学者、大谷省吾は岡本太郎の〈対極主義〉の概念の直接の成立の原因を作家・文芸評論家である花田清輝との接触にあると推察している。太郎の核にある人物とは、バタイユなのか、花田清輝なのか。結局のところどっちなのか。2019/10/29
seichan
2
バタイユとの交流(秘密結社も含め)、マンガ(岡本一平)との関係、さらにタイガー立石への言及、太陽の塔に関する丁寧な考察など、類書に見ない論がてんこもり。2001テロの影響を受けた文章も多々でてくるが、かえって後々に「時代性」を証明するものになると思う。良書です。2011/06/24
///
1
岡本太郎の思想に影響を与えたバタイユ、ヘーゲル、コジェーヴの関係が分かりやすくまとまっていて満足。2013/06/08
-
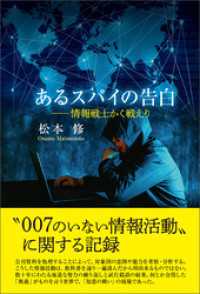
- 電子書籍
- あるスパイの告白―情報戦誌かく戦えり