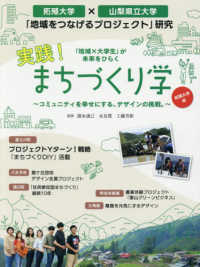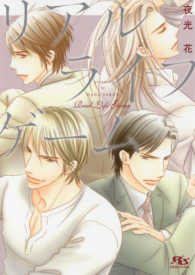出版社内容情報
日米合作の「ナショナリズム」、底からの抵抗と闘争の脈動――
〈戦後〉はいかにうみだされ、どのように生きられてきたのか。『菊と刀』の抜本的読みなおしなど、膨大な資料を縦横に駆使し、日米合作の占領が作り上げた東アジア冷戦体制とナショナリズムを再審にかけ、反戦平和運動の実践と思想のうちに豊穣な抵抗の歴史を見出す、戦後史研究の新たな展開。解説・酒井隆史
内容説明
日米合作の「ナショナリズム」、底からの抵抗と闘争の脈動―“戦後”はいかにうみだされ、どのように生きられてきたのか。『菊と刀』の抜本的読みなおしなど、膨大な資料を縦横に駆使し、日米合作の占領が作り上げた東アジア冷戦体制とナショナリズムを再審にかけ、反戦平和運動の実践と思想のうちに豊饒な抵抗の歴史を見出す、戦後史研究の新たな展開。
目次
序論―東アジアの冷戦とナショナリズムの再審
1 『菊と刀』と東アジア冷戦―あるいは「日本文化論」のパターン(研究課題―『菊と刀』;総力戦と科学動員;対日政策の形成と対日心理戦;ルース・ベネディクトと『菊と刀』の形成;日本の占領と象徴天皇制の形成 ほか)
2 「反戦平和」の戦後経験―対話と交流のためのノート(問題関心と視点;東アジア冷戦体制確立期における「反戦平和」(一九四五~五五年)
「平和共存」と「革新」の時代(一九五三~一九六四年)
ベトナム反戦運動とパラダイムの革新(一九六五~一九七四年)
「新冷戦」から冷戦の終焉へ(一九七五~一九八九年) ほか)
著者等紹介
道場親信[ミチバチカノブ]
1967年生まれ。和光大学現代人間学部教授。専門は社会運動論・日本社会科学史。2016年9月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価