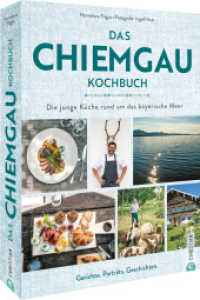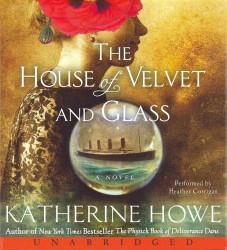- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
死霊はどのように描かれてきたのか
日本では死者が骸骨となって墓場で酒宴を開く情景が古くから描かれてきた。また蘇生・転生することで新たな人生を迎えることがあり、さらに死後、鬼と化して人間に害をなす存在となることもあるとも信じられてきた。そうした考えは近代社会において科学的に否定されながらも、その一方で根強く息づき。今日、海外では例を見ない独自の形で継承され、進展している。本書では日本において死霊がどのように描かれてきたのかという問題を通史的に示して日本人の死生観について、文化的創造の歴史的側面から照射していく。