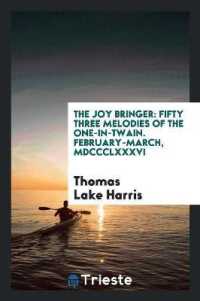出版社内容情報
日本は西洋に何を見、西洋は日本に何を見たのか。
激動の日本美術史、近代美術と文学、西洋のジャポニズム、現代のデザイン、写真、和洋住居空間まで、芸術家たちの知られざるエピソードをまじえ、日本と西洋の美術/芸術観を比較し、その文化的伝統や美意識の差異を複眼的かつ大胆に説き起こし、美の歴史を読みかえる。
高階秀爾[タカシナシュウジ]
著・文・その他
内容説明
激動の日本美術史、近代美術と文学、西洋のジャポニズム、現代のデザイン、写真、和洋住居空間まで、芸術家たちの知られざるエピソードをまじえ、日本と西洋の美術/芸術観を比較し、その文化的伝統や美意識の差異を複眼的かつ大胆に説き起こす。
目次
1 日本と西洋(マスターピースと「名物」―芸術における価値の創出;聖地と霊場 ほか)
2 江戸から明治へ(「浪裏」をめぐる幻想;江戸東京名所考 ほか)
3 画家・写真家・デザイナー(和洋二筋道の画家川村清雄;亡き妻への相聞歌 ほか)
4 文学と美術(矢代幸雄『世界に於ける日本美術の位置』;和辻哲郎『イタリア古寺巡礼』 ほか)
著者等紹介
高階秀爾[タカシナシュウジ]
1932年、東京生まれ。美術史家。2012年、文化勲章受章。国立西洋美術館館長などを経て、岡山県倉敷市・大原美術館館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ハラペコ
1
前半は比較文化、後半はイタリア、フランス、イギリスから影響を受けた日本人芸術家。本書では、中世以前の視点は「近代」からの見方を通じてしか存在せず、近代での芸術観が軸となっている。 イデア⇔漸進、天才⇔集団、聖地⇔霊場、城壁⇔襖(中間領域:軒下)、ポスターと判じ画、(名所の)恒久性⇔制限的。他、「伝統」の創出はナショナルアイデンティティの為に明治に創出された側面、絵画における人物や余白の位置。 真の国際性に民族性の必要を認めている。2025/06/05
Tad
0
日本と西洋の比較文化論。 「美意識はまた、日本人の秩序感覚、思考様式、行動原理などにもつながる問題である。」と著者が述べている通り、取り上げられているテーマは美術に限られていません。 2章で岡倉天心らの日本美術運動などついて触れられており、日本の美術を日本側の立場でどう位置づけるのかといったムーブメントについて興味深く読めました。 1章 日本と西洋 2章 江戸から明治へ 3章 画家・写真家・デザイナー 4章 文学と美術2021/07/22