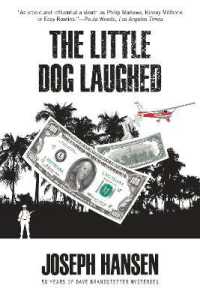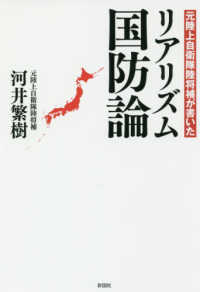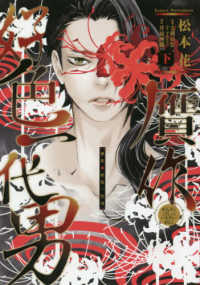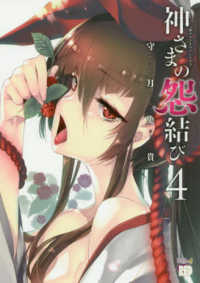内容説明
日本語ラップのオリジネイターから、新世代を担うラッパーまで、世代を横断したインタビューを通して日本語ラップの技術と歴史を俯瞰する決定版証言集。
目次
第1章 いとうせいこう―自転車に乗ってどこまでも(聞き手=磯部涼)
第2章 Zeebra―シーンを導く表現技法(聞き手=佐藤雄一)
第3章 般若―“昭和の残党”の戦い(聞き手=二木信)
第4章 漢a.k.a.GAMI×ANARCHY―“ヒップホップ”の証明 ストリートを超えて(聞き手=二木信)
第5章 KOHH―滲みだす“叫び”(聞き手=山田文大)
第6章 MARIA―パーティー・ヒップホップ・ヨコハマ(聞き手=二木信)
第7章 T‐Pablow―「内なるJ」と向かい合う(聞き手=磯部涼)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベンアル
9
2016年に書かれた本で、フリースタイルダンジョンの放送でブームとなったヒップホップについて当事者のインタビューをしながら、ヒップホップとは何かについて書かれている。j-rapはラップをしている音楽家で、ヒップホップは内面や生き様を含めたもので、自分は後者が好きだ。この本を読んだ後、久々にanarchyを聞いたら、歌詞に説得力を感じた。2023/09/01
オールドサイレンサー
6
★★★☆☆ もう少し深みがほしかった感がありますが、さらっと読めて気分転換にいいです(笑)2019/09/05
nizimasu
5
日本語ラップと言えば個人的には漢の書いた「ヒップホップドリーム」がここ最近で読んだ本の中でも屈指の肚を見せた本だと思った。ストリートというのは日本においてはなかなかイメージしづらいものだったけど彼の言葉からは地に足のついた悪さも含めての佇まいが実に堂々としていて楽しめた。彼と後輩分のアナーキーの対談は面白かったが白眉はSIMILABのマリアのインタビューで彼女の音楽はそれで好きだったけど結構、ビッチなインタビューでそれが好ましくてふむふむと読める。せいこうさんのジブラも懐かしいよね。今の文脈とは違うけど2018/11/22
U
2
短歌・和歌とラップって似ている部分が多い?と思い地元の図書館にある本で少しずつ勉強中。歌舞伎の口上にも共通点あるような。文化の発祥、表現される形が短歌や歌舞伎と異なるのに共通点があるようでラップって面白い。やはり日本人には七五調が馴染み深いのねと納得すると同時にそこからどう脱却するか試行錯誤して日本語ラップの入口を作ったせいこうさんの話は興味深い。後半にいくにつれて日本語ラップという括りを好まなそうなラッパーの話に。いろんなスタイルがあるんだな。2019/08/01
まさき
2
ユリイカ版を持っていても新たなインタビューもあるので楽しい。 特に冒頭にあったどうでもいい話しがないのがいい。 「日本語ラップ」という言葉を批判的にパブロが使ってるのも面白い。2018/03/15