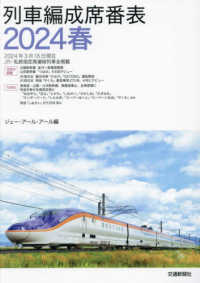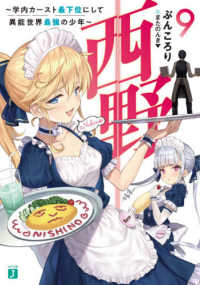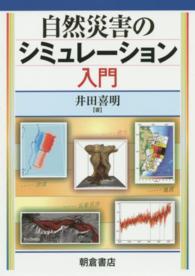出版社内容情報
ロビン・ダンバー[ロビンダンバー]
内容説明
ヒトはうわさをするために生まれた。猿の集団が大きくなって「毛づくろい」ができなくなったとき、それに代わるコミュニケーション手段として生まれたのが人間の「ゴシップ=言語」だった―生物学、脳生理学、人類学、心理学などの最新成果を踏まえ五〇〇万年を鳥瞰し、ことばの進化の歴史を根底から覆す。「ダンバー数」の定式化で注目を集める著者がことばとは何か、集団とは何かを解き明かす。
目次
1 むだ話をする人々
2 めまぐるしい社会生活へ
3 誠実になることの重要性
4 脳、群れ、進化
5 機械の中の幽霊
6 はるか彼方へ時をさかのぼる
7 最初の言葉
8 バベルの遺物
9 生活のちょっとした儀式
10 進化の傷跡
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
かんやん
25
『人類進化の謎を解き明かす』『友達の数は何人?』と同じ著者の本を読んできて、さすがにもう進化心理学はお腹一杯。毛繕いと時間収支モデルとダンバー数、心の理論(志向意識水準)のお話。理解は深まったと思うが、さすがに飽きてきた。人(自分か)は宗教とか、言語の起源をあれこれ考えてみて、仮説を建てるのが好きかも。多面的なものだから、単一の起源とは限らないし、起源の探究というのも脳のバイアスなのかなって思ったり。最後は、ダンバー先生、風呂敷広げすぎて、散漫になってるような。2020/09/30
M
8
他の霊長類の社会生活が1日の大半を特別な相手との毛づくろいに従事することから、人間でそれに相当すると考えられる言語は様々な観点から、安上がりで極めて効果的な毛づくろいに代替していることに着目し、従来の言語の物語るという性質よりも、その発達の経緯は噂話によるフリーライダーの動静を知ることで、社会的安定を維持するためではないかと仮説立て、その検証のため様々な集団の性質と規模の特徴を観察すると、其々に対応する人数に共通性があること、会話内容などでも男女ともに個別的な話題に関する割合が10%ということを発見した2020/07/14
smatsu
4
ダンバー数で有名な著者による進化心理学の名著です。p268に著者自身が内容をまとめています。霊長類の社会的群れの規模は新皮質の大きさによって決まり人間の社会的ネットワークのノード数は約150。霊長類の群れを維持するための必要な「社会的毛づくろい」の重要性の指摘。それに費やす時間は群れの規模に正比例する。言語は人間が大規模な毛づくろいの時間を割けなくなったことからその代替物として進化し、社会的な毛づくろいに取ってかわったものである。一度に親密な会話ができるのは4人のグループまでで、一度に一人しか発言できない2022/08/14
sayan
4
猿の「毛づくろい」から話がはじまる。どうここから言葉の起源というテーマに近づいていくのかと思いきや、今度は話が「ゴシップ」にうつる。なんのこっちゃと思いきや、ぼーっと読んでいると唐突に結論が述べられる。つまり、「毛づくろい」に変わるコミュニケーション手段としてうまれのが「ゴシップ=言葉」であると。様々な分野に論拠を求め、一見とっつきにくいようにも見えるが文体はいたって平文で語り口は非常に面白かった。こういう考え方もあるね、と、まあ猿から進化したのだし…とアカデミックな読み物だけれど楽しめた。2016/11/05
つっきーよ
3
猿は一日の20%を毛づくろいに使う。猿の毛づくろいは肌を清潔に保つ以外に社交の意味があり、互いに毛づくろいをした猿は協力関係を築きやすい。猿の毛づくろいの代わりに現生人類は言語を発達させ、一日の40%を社交に使う。毛づくろいは一対一でしかできないが、会話は多くて4人までは参加できる。チンパンジーの群れが50匹程度であるが、人間は最大150人程度のグループを作る事ができ、それは言語による恩恵と考えられる。 毛づくろいの話までは興味深かったが、後半は良くある進化心理学の話で少々物足りなかった。2023/07/16