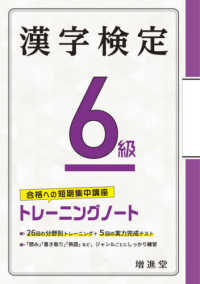内容説明
1960年代、精神医療批判の運動があった。それは当時の社会変革運動の流れに深く関わりながら、従来の制度や治療法への激烈な造反として噴出した。ロボトミー手術、電気ショック療法、薬物療法などへの糾弾から、開放病棟の試み、および地域医療の実践も展開された。関係者の証言、膨大な文献資料を掘り起こし、いまだ正解の見えない精神医療と社会の関係に鋭いメスを入れる、圧巻の現代史。
目次
序章
第1章 前史・既に言われたこと
第2章 造反:挿話と補遺
第3章 各種療法、とくにロボトミーに対する遅くになされた批判
第4章 「生活療法」を巡って
第5章 何を言った/言えるか
著者等紹介
立岩真也[タテイワシンヤ]
1960年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。現在、立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。専攻:社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
春風
10
ひどい悪文で、何を指しているのかわからない指示代名詞など意味がとれない箇所もちらほら。この時代の精神医療史の記録は一方的な回想以外なかったので貴重だけど、ほぼ文献のみに依拠して取材をほとんどしていないらしい姿勢は疑問。書かれたことより書かれなかったことの方が多いだろうから。存命の関係者も減ってきているのだから、はやいうちに精神医療に詳しいルポライターに書いてほしい。2014/06/07
ktytnd
2
文章に癖があると思ったが、書かれていることは面白い。戦後における精神医療から、そもそも病とは何か、社会のために精神障害者を隔離することは許されるのか、ということまで話は広がるが、こうしたことは解決不可能ではないかとも感じさせられる。ただもちろんそれでよい訳ではない。2014/03/31
YASU
1
読みにくい,疲れた,わかりにくい.しかしこの精神医療をめぐる正統派と造反派の争いそのもの,ひいては精神医療とは何かという問いそのものが未だ解明されることのない謎なのだと,著者は言いたいのだろうと忖度すれば,このまわりくどい書き方もしょうがないのかと,立岩贔屓の私としては考えてしまう.2020/02/01
石橋
0
半分以上が引用で読みにくいのはもちろんだが、全体的に冗長すぎて冷静に読めない。「障害、精神病の定義」については今も論議があるし、しなければならないが、筆者の論調では永遠に平行線だと思う。2017/11/18
ぬう
0
あーん ? 「社会防衛」という言葉は、ある人々にとっては自動的に否定的な言葉である。同時にある人々にとっては自明に肯定的な言葉である。 ( т т )2025/06/27
-

- 電子書籍
- キミの前でキミ以外を抱く【単話版】(1…
-
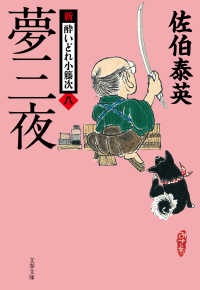
- 電子書籍
- 夢三夜 新・酔いどれ小籐次(八) 文春…