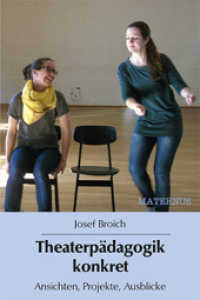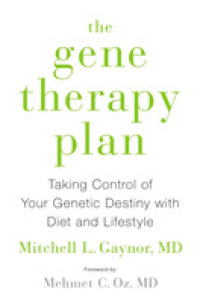内容説明
日本人がこよなく愛すウナギの食文化を絶やさないために、考えを持ち寄り、議論を尽くそうではないか。この趣旨に賛同した各界のキーパーソンたち―養殖業者、シラスウナギ漁業者、研究者、行政、メディアが一堂に会した画期的シンポジウム、待望の書籍化。
目次
GCOEアジア保全生態学からの挨拶
基調講演「ニホンウナギとともに生きる」
1 日本のウナギの現状(日本人はウナギをどう食べてきたのか;ニホンウナギの資源調査について;IUCNウナギレッドリスト会議報告;ウナギの情報と経済;産卵場調査から予測するニホンウナギの未来 ほか)
2 資源回復への試み―ステークホルダーからの提言(漁業者の役割―蘇るか浜名湖ウナギ;養鰻業界の役割―養鰻業界が行なっているウナギ資源保護対策;蒲焼商の役割;報道の役割―ウナギ問題をどう伝えるか;環境行政の役割―環境省第4次レッドリストについて ほか)
総合討論 人間とウナギこれからのつき合い方
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
55
うな丼が好きな人や鰻に興味があるひとにおすすめしたいほんになっている!この本はうなぎが絶滅危惧種になってしまいどうやって立て直すかを考えるシンポジウムの様子をまとめた本になっている!うなぎの種類やうなぎの未来について語っておりとても面白かった!うなぎがどうなるのかこれからも注視していきたい!2023/12/21
WATA
36
東京大学で行われたシンポジウムの様子を活字化した本。研究者・漁業組合・蒲焼店の組合・官公庁などが、それぞれの立場からウナギの生態系維持について発言している。本書を読んで感じるのは、私も含めた消費者にはウナギの危機的状況が伝わっていないということ。ウナギの完全養殖は研究室でしか成功しておらず、スーパーで売っている養殖ウナギは海で捕れたウナギの子供を育てているだけであること、乱獲によりヨーロッパのウナギは絶滅寸前になり、その代わりに今度は東南アジアのウナギが大量に捕獲・輸入されていることなどは知らなかった。2014/03/29
ぼのまり
7
鰻って、絶滅危惧種でレッドリストにも載ってるんだということをあらためて知る1冊。なかなか美味しい鰻を口にする機に恵まれないが、日本人の食文化を見直すきっかけを与えてくれる本だと思う。2014/01/05
manabukimoto
4
『うな丼の未来』 鰻ではなく、うな丼の未来という題名が示唆する様に、魚としての鰻と云うよりも鰻を食する文化を論じた東大でのシンポジウムを一冊の本にまとめたもの。養殖と云っても元のシラスウナギは100%天然のものを使用している。そこが牛やブロイラーとは違う。少なくとも完全養殖が可能になるまでは、ハンバーガーや牛丼と同じ食べ物としての扱いは避けるべき。ハレの日のご馳走として、鰻を食べよう!という趣旨の意見。私も今年鰻を食べたのは一回きり。肥後橋の「だい富」で、うな重3000円。それで、いいのでは。納得の書。2013/11/29
123456789wanko
3
2013年7月に開催された鰻に関するあらゆる人々を集めた会議の模様を収録。いかに鰻が危機的状況にあるのかよくわかる。現在日本鰻は国内では絶滅危惧種であり、ヨーロッパ鰻もほぼ同様の状態である。このままでは世界的にも絶滅危惧種に、そしてワシントン条約登録にもなりかねない。われわれ消費者も、まずはこの現状を知ったうえで、子孫が美味しくうな丼を食べられるようにしなければならない。2014/05/04
-
- 洋書
- Limberlost