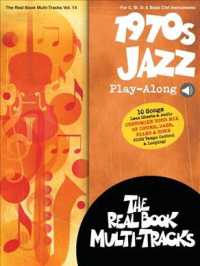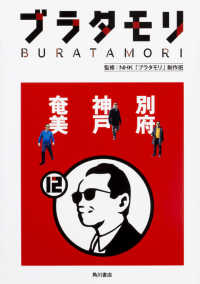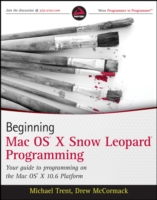内容説明
魚型ロボットにライフゲームをプレーさせてみた。進化研究の難問は、生命の歴史が過去に埋もれていることだ。今日見えている適応した状態をつくりあげた劇的な出来事を私たちは目撃することはできない。ところが、バイオロボット工学者である著者は、この問題を克服する方法を思いついた。絶滅した動物に似たロボットをつくって進化圧をかけ、配偶者や資源をめぐって争わせて「遺伝子」を変異させるのだ!
目次
1 なぜロボットか
2 生命のゲーム
3 エヴォルヴァボットの開発
4 生命のゲームをプレーするタドロ
5 身体性の心の生活
6 捕食者、被捕食者、脊椎骨
7 進化トレッカー
8 さようなら、そしてロボット魚をありがとう
著者等紹介
ロング,ジョン・H.[ロング,ジョンH.] [Long,John H.]
アメリカの生物学・認知科学者。ヴァッサー大学教授で学際ロボット工学研究所の所長も務める
松浦俊輔[マツウラシュンスケ]
翻訳家。名古屋学芸大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
1
プログラムによるライフゲームの話は勿論聞いたことがあったけれど、それを実際のロボットでやってみようという話。どうしてデジタルで出来るのにあえて現物で? という当たり前の疑問が出るけれど、著者もそこにはきちんと向き合っている。デジタルだと「(気づかないまま)物理法則に反することが出来る」「周辺環境との相互作用が考慮されないか減る」という。多分両者は同じことの程度の違いだと思う。また、大部分が魚ロボットの設定などに費やされるので、魚ロボットで「なにを」調べようとしているのか、つぶさに見ることが出来て面白い。2013/09/23
ぬばた
0
魚の尻尾の進化を追っていたら、魚型ロボットを作ることになって、最後は静音性の高い船の推進機関ができたとのこと。2014/10/30
-
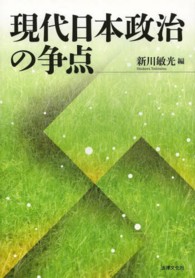
- 和書
- 現代日本政治の争点