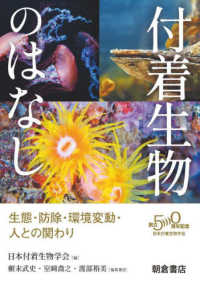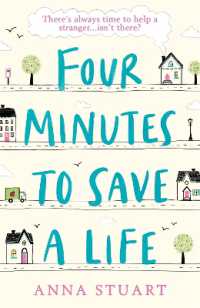内容説明
木の枝を這うイモムシから勇気をもらったいじめられっ子のぼくは、動物学者になろうと決意。チョウ、セミ、ダニから小鳥やサルやウシ、単細胞動物から脊椎動物まで、さまざまな生命たちの生きるひたむきさと厳しさの数々は、文句なしの感動を呼ぶ。生き物の目線から見た大自然の美しさのエピソードを豊かに伝える、日高ワールドの自伝的エッセイ群。
目次
プロローグ 動物は何を見ているか
1(青春の道標;思っていたこと思っていること;風知草;食のこぼれ話 ほか)
2(動物の眼り;美しさの自然誌;環境と環世界;動物行動学から見た二十一世紀)
エピローグ 小さな電車を見下ろす家
著者等紹介
日高敏隆[ヒダカトシタカ]
1930‐2009年。東京生まれ。東京大学理学部卒業。専攻は動物学。京都大学理学部部長。滋賀県立大学初代学長、総合地球環境学研究所初代所長等を歴任。ティンバーゲン、ローレンツ、ドーキンスらの日本への紹介者としても知られている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
79
2016年110冊め。体が弱く運動が苦手なために「お国のために役立ちそうにない」と、小学校の校長に毎日蹴られ、両親も信用できずに自殺をしようとしていた少年が、近くの原っぱで「おまえ、いったいどこ行くの」と芋虫に問いかける。一生懸命生きる虫に同調して、虫になれば生きていけると気づく。昆虫が、彼の生きる導となった。「科学とは主観を客観に仕立て上げる手続き」の名言。日高先生が柳田國男先生宅に下宿されていたとは驚きだ。戦後のころの大学はなんと楽しそうなことか。ちょっとその当時の男子大学生になってみたい。2016/02/20
AICHAN
39
図書館本。日本の動物行動学の第一人者だった故日高敏隆さんの自伝的エッセイと、教育などについてのエッセイ。「“科学する心”ということばが大嫌いである」。そのココロは「科学とは主観を客観に仕立て上げる手続き」だから。「子どもを育てるのではなく、子どもが自分で育っていける状態をどう作るか、それが問題である。子どもが“なぜ? どうして?”とたずねたとき、それにすぐさま答えてやる必要はない。“そういえばたしかにふしぎだねえ”と同感してやればいい」。確かにそうだ。2023/01/16
UK
24
動物学者のエッセイ。色々なところに書いたものを集めたものなので、同じ話題の繰り返しも結構多く、また深さという点でもあまり掘り下げたものではないとわかり、いささか期待はずれ。蝶はどこを選んで飛んでいるのか、クローンはNGと自然は何億年も前に答えを出している、など興味深いテーマは多い。軽いエッセイではなく、もっとちゃんと書かれた本が読みたくなる。 2016/03/25
トムトム
13
あとがきを日高先生と仲良しだった心理学者さんが書いている。この本に書いてあるような内容、生き物をやっている人には当たり前。でも心理学者さんには素直に肯定できないそうな。日高先生とどんなに長時間お話しても、人間だけを相手にしている心理学者さんには通じない。不思議です。2019/11/13
とろこ
8
動物学者、日高さんのエッセイ。日中戦争とかぶっていた学生時代のこと、「ちょうちょの飛ぶ道筋」という実益のない(なさそうに見える)研究について、自然界のさまざまな不思議、教育問題… やさしい語り口ですが視点がするどいので、「へぇー!」の連続です。もう亡くなった方なのが残念で仕方ない。 最近いろいろ悩んでいたことが、答えが書いてあったわけではないけれどなんだかすっきりして、勇気が出ました。このタイミングで出会えて良かった。2013/05/15