- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
生命システムの謎に挑みつづける「オートポイエーシス」の構想。片麻痺や発達障害といった脳神経系障害とリハビリテーションの現場で、「意識」や「行為」の概念が新たに定式化され拡張していく。あらゆる人間の生の深層に届く言葉を繰り出す唯一無二の知の実践。
目次
行為のシステム現象学へ
1 出発―「知る」を解除する(意識;身体動作;創発)
2 エクササイズ―臨床のさなかの認知行為(免疫システム;障害;リハビリテーション;発達)
3 拡張―触覚的世界へ(空間;触覚)
アラカワの方法
著者等紹介
河本英夫[カワモトヒデオ]
1953年、鳥取県生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。現在、東洋大学文学部教授。専攻は科学論・システム論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
4
リハビリテーションで患者が動かない肩を動かそうとする場面では、快不快の区別が起こる。不快を避けるこの選択を著者は認知以前の行為と見做す。ここから著者は意識を、選択を可能にするが選択が起こる際は邪魔になる「遅延機能」と捉える。この機能が働くうちは選択は抑え込まれ、モードが変わると選択が起こるからだ。本書は、意識が気づかない自己の組織化としての選択行為を、自己自身を区切るプロセスと捉える。ここから展開可能な自己があるとするならば、境界を区切り続け、「みずから自身を繰り返さない」(デュシャン)自己が導出される。2017/09/27
engawa
3
私たちの身体は、私たちの意識とは異なる能動性で動いている。また、言葉とは違う論理で動いたいるため、言葉にそのまま写し取ることはできない。地上に生をうけた身体は、重力の中、空気と共棲して生き、意識、そして自己意識まで生み出す。そんな身体の姿に、オートポイエーシスの理論や、著者が関わっているリハビリテーション医学実践の現場での経験等を持ち、踏み込んでいく。あくまで実際に使える身体像を創ろうと。その考えは、ドゥルーズにも繋がっている。面白いが、自分には、一読しただけで分かるような本ではない。2011/01/24
-

- 電子書籍
- やがて君になる【タテスク】 Chapt…
-
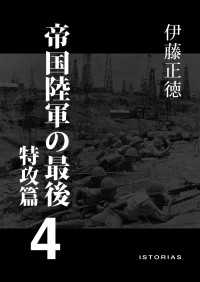
- 電子書籍
- 帝国陸軍の最後 4 特攻篇







