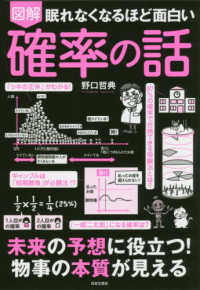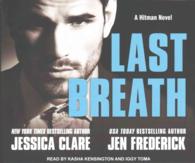内容説明
全世界を席捲する食糧ビッグ・ビジネスによる食の伝統と慣習の破壊は、南北問題をさらに拡大し格差増長に走る。地産地消、脱農薬、スローフード、環境問題、フェア・トレードなど食の多彩な局面から、「本当の」美味しい食べ物の生産そして消費は如何にあるべきかを提言する。
目次
1 食は命の源、それゆえ、なすべきことはなさねばならない
2 戦後の夢とその挫折
3 食糧主権を適切に位置づける
4 パンとバラ
5 非情な自由貿易と安価な食糧
6 食糧問題の経済学
7 今すぐ決断しなければならない
著者等紹介
ロバーツ,ウェイン[ロバーツ,ウェイン][Roberts,Wayne]
カナダ在住のジャーナリスト、「NOW」マガジン常連執筆者。食糧システムの実践的アクティヴィスト。カナダ食糧安全保障連合、トロント食糧政策評議会などの活動により市民の支持を勝ち得ている
久保儀明[クボヨシアキ]
翻訳家。東京外国語大学卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Francis
2
近代、特に1970年代以降、栽培技術や流通の変革により農産物が安価になった代償として、飽食と飢餓、耕作地の荒廃などの弊害がもたらされ、それに対抗する動きとして、スローフード、有機農法、フェアトレードなどが第三世界を中心に活発化していることを述べる。危機を煽る本の題名だか危機を解決する方法も述べられており、あまり適切でない題名かも。現代の食糧問題について非常によく分かる良著だと思う。2014/05/12
isao_key
2
食糧の流通や産業、政策などについての問題に視点をおいた本。著者は1970年代の低価格食料革命によって、食糧に関する状況そのものも激変したという。安価な食事は簡便性や、主婦から家事のわずらわしさを軽減したが、それに代わる代償も大きかった。<不健康な食生活から発現するすべてのガンのうち3分の1を占めている大腸ガンは、その種の食生活を長期にわたって続けた結果だということが明らかにされている。>(p.192)われわれ一人ひとりが、食糧に対して責任を負っているという認識を持つことが大切であることを気づかせてくれる。2012/07/27