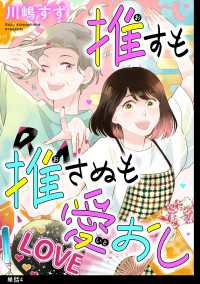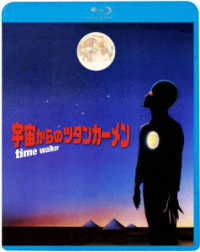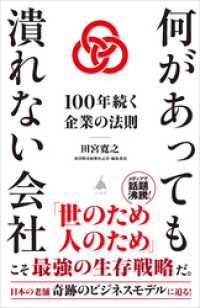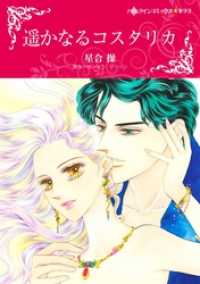内容説明
なぜ“霊”が写るのか。宗教・科学・芸術の交差点において大きな影響を与えてきた心霊写真。その詳細を追いながら、社会的・文化的側面を考察する、あまりにも斬新で前例のない研究書。図版多数収録。
目次
第1章 宗教(宗教における霊;幻像と霊;聖遺物と霊;聖像と継続;クロスオーヴァー―典礼から交霊会へ;残像―死と欲望;死後―行き先と悪霊)
第2章 科学(進展―交霊会から科学へ;露出―霊の検証;写真の媒体)
第3章 芸術(霊と芸術;写真師と霊;霊と捏造;未来の(クリスマスの)亡霊
霊の軍団―修正と多様化)
著者等紹介
ハーヴェイ,ジョン[ハーヴェイ,ジョン][Harvey,John]
ウェールズ大学アバラストウィス校教授。美術史家、アーティスト。宗教における視覚文化の研究、現代美術、ウェールズの芸術などが専門
松田和也[マツダカズヤ]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
163
以前読んだ本に、日本の写真は着物が縁起の悪い左前に写ることから魂を抜き取られるという俗信が生じ、それが失敗写真を心霊写真と思い込む端緒になったとあった。欧米の心霊写真は、宗教と科学の結合から生まれたようだ。それは死後生への畏怖や祝意と結びつき、遺族に慰めをもたらす媒体として商業化していく。宗教記号を採り入れつつ、一方では科学による未知への探求に対する期待に応えた。また北米発祥の心霊主義は、悔い改める者と改めぬ者を分断する教義とは違い、誰もが平等に導かれ向上する霊性観を説いたが、心霊写真はその証ともなった。2025/10/18
紫
2
宗教、科学、美術…三つの視点から社会史的に読み解く心霊写真研究本。軽い好奇心で飛びついたら、神秘思想や心霊研究の解説についていけなくてチンプンカンプンになってしまうかも。本書ではふんだんに心霊写真が掲載されていますが、これが怖いより、不思議より、気持ち悪いものばかり。なまじチープで、どうしてこんなものを作るのか意味が分からないだけにただただ気持ち悪いのであります。インチキだとは分かっていてもトラウマモノの気持ち悪さ。生理的に気持ち悪いものがダメな方は何とぞ御注意を。星3つ。2017/09/29
春色
2
心霊写真が何故生まれ、現在に至るまで生き延びてきたのかの考察。合理主義の台頭によって力を失った教会に代わる「死後の世界が存在することの証明」として心霊主義が生まれ、支持されてきたと言うのは納得できるのと同時に切ない話。/図版も多くて大変結構なんだけど、訳文がツライ。2009/09/25
紅独歩
2
「「偶然写ってしまった心霊写真」ではなく、明確な意図をもって写された(あるいは製作された)心霊写真が主題。したがってその真贋は問題にせず、「宗教」「科学」「芸術」において心霊写真が果たした役割を探る。その考察は非常に興味深いものの、やや訳文が硬いように感じられた。サブカルチャーではない心霊写真の世界を知るには良い。2009/06/11
monado
1
宗教、科学、芸術の視点からみた心霊写真の文化史。幽霊のヴィジュアルが半透明になったのは『クリスマスキャロル』の影響、など面白い記述多数。2011/10/23