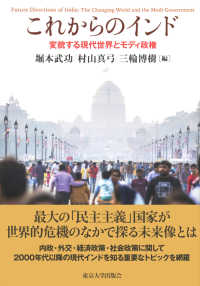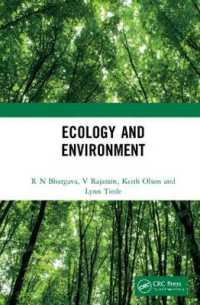内容説明
心が病むとはどういうことか。人間とはなにか。われわれの心とはどんなものなのか。フロイトの理論と方法を、精神分裂病の臨床研究に応用し、無意識の構造に光をあてて、精神分析学に新たな地平をひらいた古典的名著。
目次
精神病の内容
心理学的了解について
早発性痴呆の心理(早発性痴呆の心理についての理論;コンプレックスと心に対するその作用;連想に及ぼすコンプレックスの影響;早発性痴呆とヒステリー;妄想性痴呆の一例)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
統合失調症の症例研究や治療から出発した著者は、その初期にはヒステリーや神経症に効果があるフロイトの無意識に対するアプローチに従っていたことが本書でわかる。「私はスイスです」という患者の言葉も、フロイト的な自由連想から隠喩の連鎖として(「私は自由の国スイスのように自由です」)解釈する。一方「早発性痴呆の心理」という論文にはフロイト的分析が及ばなくなる場面で「神話的思考」の存在を仄めかす言葉があり、心をシステムと捉え、個人を超えた超越機能として集合的無意識を設定する契機となるような元型論の発想も混在している。2021/06/23
らい
8
古本屋にあったから手に取った。メインの症例の細かい分析については、なんとなくにしか読んでないけど、1900年前後のこの界隈の事情が少しずつ見えてきたのは嬉しい。前に読んだユングは強烈にフロイトを批判していたから、その印象が強かったけど、はじめは先生と仰いで、感銘を受けていたのか。今でこそ作り上げたどデカい体系が前提にさえなっているけど、この時はまだ精神科の臨床医で、手探りに方法論を見つけていってる雰囲気も味わえておもしろかった。2021/03/14
有沢翔治@文芸同人誌配布中
4
フロイトはヒステリーを研究するにあたって、自由連想法という言葉の連想から無意識を探ろうとしました。それを精神分裂病*1に応用したユング。その臨床例と分析記録です。連想にかかった時間などにも意識を向けています。 後にユングはフロイトと訣別するのですが、その違いを語った講演も収録されています。https://shoji-arisawa.blog.jp/archives/51135848.html2010/11/10