内容説明
孤独で気ままな小さな足どりの読書が、野火のように豪勢に世界を燃えあがらせる―。「亡命と流浪の書物」を旅する翻訳文学者の、みずみずしい思索の軌跡。
目次
1 翻訳という手仕事(鳥のように獣のように―国境・沙漠・翻訳;鳥でもなく獣でもなく―翻訳という傷;翻訳人、新しいヨナたち ほか)
2 亡命と流浪の記述(流浪する響き;Two home Islands―二冊のエグジログラフィ;火山が私を生んだ―ギャレット・ホンゴー;チカーノ・アパッチの肖像―ジミー・サンティアゴ・バカ ほか)
3 批評としての移動(移住、外国語、批評、スペインのように見えた、でもそこは―ヘミングウェイと「異郷」;Fogo,agua,vida(火、水、生)―吉増剛造、エレメントの闘争
ワイキキのジョルジオ―ホルヘ・ルイス・ボルヘス ほか)
著者等紹介
管啓次郎[スガケイジロウ]
1958年生まれ。翻訳者、エッセイスト。ワシントン大学(シアトル)博士論文提出資格取得。現在、明治大学理工学部助教授(英語+フランス語+文化研究)。専攻分野は比較詩学、多言語モダニズム、南北アメリカ比較文学。1981年から1998年まで、そのほとんどを、アメリカ深南部、ブラジル、ハワイ、ニューメキシコ、シアトル、アリゾナで暮らす。近年は、現代のエグジログラフィ(移民・亡命者の文学)の翻訳に継続的に取り組んでいる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スミス市松
18
訪れた土地の紋様や出会った人々の印象が「私」の意識を規定していくならば、人との交流が阻まれる現在、私たちは様々な記憶を消失し自分が何者であったかすら忘却しかねない危機に陥っている。この状況に立ち向かうためにはかつてを思い出し遠くを想像しなければならないはずで、その意味で、不在のものを指し示す「文」を手がかりとした想像であり現実世界から必ず一歩引いた地平を歩む文学は必要だとする著者の主張に私は同意する。生き方のスタイルとしての翻訳を示し世界をわたってゆくすべての人に捧げられた、いわば生を読むことの実践論だ。2020/11/07
gu
3
よく知らない国のあまり聞いたことのない作家の文章を読むこと自体が面白いし、価値のあることだと思う。単一の言語で書かれたものにすら、異なる言語や文化が反響しているという。「ぼくはある意味では絶望的なまでに平坦な終着点を演出していた。ある意味では、翻訳とは平面への投影にすぎない」葛藤を持って訳さなければいけないし、後ろめたさや異質な日本語への抵抗感、あと翻訳家に対する感謝の気持ちを持って読まなければいけない。たぶん。2011/11/12
takao
2
ふむ2025/01/26
niaruni
1
「翻訳とは鳥の国からも獣の国からも追放されたコウモリの地帯の仕事」ならば、翻訳という仕事もまた「あらかじめ強いられた流浪」であるのかもしれない。2010/12/22
agrippa69
1
ツヴェタン・トドロフの逸話が印象に残った。以下抜粋「・・・トドロフはブルガリアのナショナリズムについての論文発表を求められる。彼は草稿をフランス語で準備し、ついでそれをブルガリア語に翻訳しようとしてーゆきづまる。フランス人に対してはフランス人、ブルガリア人に対してはブルガリア人になりきって対応することのできる彼だが、自分がフランス語を使用する時とブルガリア語を使用するときでは仮想された聴衆=読書がまったく違うことに、ここで初めて気付き、とまどうのだ。」2010/04/12
-

- 電子書籍
- 不実な恋人【分冊】 9巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- 情熱のとき【分冊】 8巻 ハーレクイン…
-

- 電子書籍
- 俳優Aの女たち【マイクロ】~若手喰いの…
-
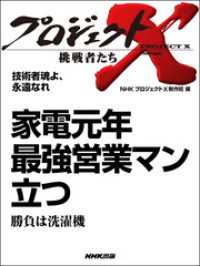
- 電子書籍
- 「家電元年 最強営業マン立つ」~勝負は…





