- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
「真の唯物論者」ベルクソンとともに、現代思想の核心概念「差異」を正面から論じる、ドゥルーズ哲学の出発点にして、その全軌跡が凝縮された驚くべき論考。ベルクソンの全体像を論じた稀覯の初期論考を併録。
目次
差異について
ベルクソン1859‐1941
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Z
7
良書。核心をついた論考と思う。ベルクソンの方法は直感であった。それは差異というのを捉えるためである。科学と哲学を対立させる場合、科学が事実を担うとすれば、哲学の役割はその吟味、空想の打破、人間的な意味の考察にでもなるだろう。ベルクソンにとって哲学とは事実のもう一つの担い手であった。ベルクソンが科学を批判するなら、それは科学が本性の差異を程度の差異に置き換える時である。程度の差異は質的あるいは量的に異なる事物の間にある。本性の差異とは同一事物内における時間内の差異である。直感は存在を物と持続という2つの層で2018/03/14
yozora
2
ベルクソンの概念ではあるがドゥルーズ思想の根幹をなす「差異」の考え方についての論考。他のものとの違いを為す差異は実際は自らの中にある。可能的なものではなく、潜在的なものに焦点を当てるこの姿勢はとても面白かったし、日常世界を思い出して実感も湧いた。ただ専門用語が多いところで疲れてしまった。2011/07/15
Yuki
1
むっず(笑)※ブログにコメントあり2018/08/01
SQT
1
人間の内的本性は差異である。単一的なものの分化、つまり潜在性の実現によってそれは達成される。この潜在性とは例えば純粋追憶である。というのは純粋追憶は過去を現在の中に延長する持続であり、それをさせるのが収縮作用で、それが差異を示すからだ。この収縮における繰り返しの要素は自己と共存する。それが収縮の程度を定義し、その程度が共存の水準を規定し、その全体が共存によって記憶を形成するからだ。この溶融を指す収縮、つまり示される差異がエラン・ヴィルタールとなる。2016/08/05
ときお
0
分かりそうで分からない。要再読。程度って何や。2016/05/27
-
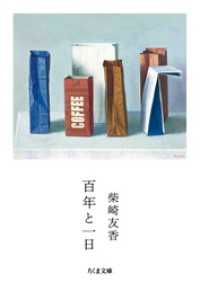
- 電子書籍
- 百年と一日 ちくま文庫








