内容説明
現代数学界の鬼才スペンサー=ブラウンの算法を導きの糸に「自己組織性」のパラドックスを乗り越え、レヴィ=ストロースの人類学、ラカンの精神分析さらには折口信夫の「まれびと論」、ヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」、バタイユの「至高性」などが描き出す社会の全事象を一つの視野に収斂させる驚異の社会システム論。
目次
0 始源
1 区別と存在
2 指し示しの算法
3 書かれざる囲い
4 自己指示的形式
5 再参入の身体的基底
6 時間の生成
7 意味の伝達=贈与
8 王権の存立機制
9 終結
* 回帰―宇宙形式の微分方程式
増補 日本語の言説空間の雑種性をめぐって
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
12
大澤真幸のデビュー作にして、以後の著作の基本理論をすでに完成させている。世界に差異を穿つ行為=指し示しが自己の身体という存在を定立させ、その定立によって・定立の前提としての他者と差異の地平も開ける。それによる他者と自己の不安定さから世界や第三者の審級が生成される、という存在論から社会システム論への移行を一挙に描きながら、そうした「存在論の抽象的な論理形式」を形にする、という極めて独創的な論考。厄介な部分、難解な部分を大量に含みながらも、わかるところは圧倒的に面白い2013/09/03
村上直樹
1
「だれもわたしに問わなければ、わたしは. 知っている。しかし、だれか問うものに説明しようとすると、わたしは. 知らないのである。」←第三者の審級。2013/03/01
soto
1
やや流し読みだが、すごい本だった。大澤さんの思索のベースがまさにここにあるのだろう。強力かつ非常に一般性の高い理論を構築している。そんな視点を若いうちにしっかり確立すれば、その後に見えてくることや考えるべきものごとも、おのずと明らかになっていく部分が多いのだろうな。ただ、この本の理論があまりに強力すぎる故に、著者は無駄にいろいろ悩まなくてもよくなりそうなので、そんな人生ってどのくらい面白いのだろうか、とも思ったりした。2011/03/08
ke_ta
0
『形式の法則』の二次創作(ブール代数の三次創作) ルーマン、ラカン、ウィトゲンシュタイン、マクタガート、折口信夫、etc...をスペンサー=ブラウンの代数にこじつけまくり なかなか読んでて楽しい2010/08/07
-
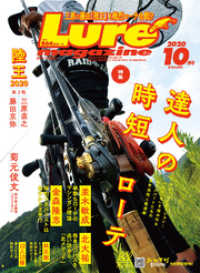
- 電子書籍
- ルアーマガジン2020年10月号





