内容説明
国家間の紛争から企業や個人間の対立する利害までを、数学的に解析するゲーム理論。その成立と展開を、創始者フォン・ノイマンの生涯に、冷戦時代の米ソ対立を重ねて描いた興味つきないドキュメント。
目次
ジレンマ
ジョン・フォン・ノイマン
ゲーム理論
核爆弾
ランド研究所
囚人のジレンマ
1950年
ゲーム理論への不満
フォン・ノイマンの晩年
チキンとキューバ危機〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
159
ゲームの理論の大家であるフォン・ノイマンの生涯と、その当時の世界の冷戦状況を対比しながら理論も若干説明されています。ですので本格的に勉強しようという方はさらに彼の「ゲームの理論と経済行動」(味もそっけもない数式だらけの本なので、私は途中でダウンしていますが)という主著を読まれた方がいいと思います。この「囚人のジレンマ」は、時たまトピックスや例題のようなものが収められているので興味深く読み続けることができました。2017/01/15
金吾
21
ノイマンの生涯を追いながら、ゲーム理論へのアプローチや補完を付け加えていきます。理論そのものには深い考察はありませんが、ゲーム理論を全然知らない私にとっては取っつきやすかったです。「囚人のジレンマ」「ドルオークション」が良かったです。2021/08/12
凛
12
フォン・ノイマンとゲーム理論のミニタリー風味なドキュメンタリー。核兵器開発に携わりゲーム理論を展開させたフォン・ノイマンが主軸なので、軍事的な話題が大半を占めている。政府、科学者、そして世界中の人々を悩ます兵器開発と戦争のジレンマが最も印象深く、メッセージ性も強かった。ゲーム理論の話題は「社会のジレンマ」とアクセルロッドの実験、「ドルオークション」「最大数ゲーム」が面白かった。あと忘れられないのは、ビキニの語源。2015/01/10
ゆとりくん
6
「ゲーム理論学史」である。ゲーム理論は解釈の学問であり、問題に対して解決策を提示しうるものではないと思った。それは、ジレンマを起こす対象が、「合理的」でないことに要因がある。そもそも合理性とは何かという定義付けが明確でない以上、そこにゲーム理論の課題があり、解決の学とはなりえないと言える。ただ、解釈学は人文系の領域とされていたが、ノイマンが数学的な解釈の方法を開発したことは、図式の一つが増えた点で大きな成果である。他の学問分野にも応用されているように、非常に柔軟性のある理論であり、知っていて損はしない。2012/12/02
河童
4
各所で論じられる「囚人のジレンマ」。整理しておくのにちょうどよい本でした。2015/10/22
-
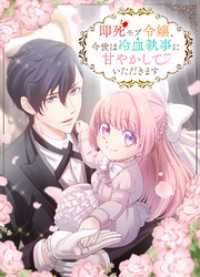
- 電子書籍
- 即死モブ令嬢、今世は冷血執事に甘やかし…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢のモテ期【タテヨミ】第18話 …
-

- 電子書籍
- 皇帝エンディングでいきます【タテヨミ】…
-
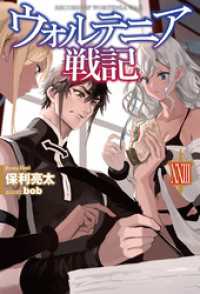
- 電子書籍
- ウォルテニア戦記 XXIII HJノベ…
-
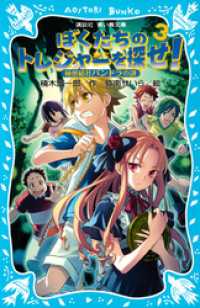
- 電子書籍
- ぼくたちのトレジャーを探せ!(3) 秘…




