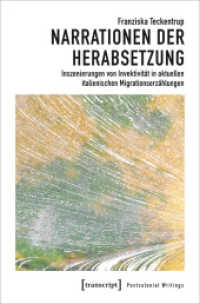内容説明
「非自己」から「自己」を区別して、個体のアイデンティティを決定する免疫。臓器移植、アレルギー、エイズなどの社会的問題との関わりのなかで、「自己」の成立、崩壊のあとをたどり、個体の生命を問う。
目次
第1章 脳の「自己」と身体の「自己」
第2章 免疫の「自己」中心性―胸腺と免疫の内部世界
第3章 免疫の認識論―ネットワーク説をめぐって
第4章 体制としての免疫―インターロイキン王国の興亡
第5章 超システムとしての免疫―自己の成立機構
第6章 スーパー人間の崩壊―免疫系の老化
第7章 エイズと文化―RNAウイルス遺伝子の謀略
第8章 アレルギーの時代―あるいは相互拒否の論理
第9章 内なる外―管としての人間
第10章 免疫系の叛乱―自己寛容と自己免疫
第11章 免疫からの逃亡―癌はなぜ排除されないか
第12章 解体された「自己」―再び「自己」について
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カザリ
55
すごい。。一読してもほとんど理解できず。。なんだろうな、おもしろいんだけど、まだわからないので、再読決定。あとどう著者の全集がでたばかりなので、買う。。免疫からシステム論まで語っているのが、面白い。。生命ってすごい。。健康にきをつけて、もっと免疫たちを働かせようと思いました(笑)2017/06/05
翔亀
45
【コロナ26】1993年刊というから30年近く前の本。当時、医学に全く関心がなかった私でも、現代思想・哲学界での評判(青土社『現代思想』連載。自己とは何かという問い)を聞いて購入したが積読。その後、多田さんは能の世界でも著名だったことを知り、晩年のリハビリ闘争も注目を浴びたことも知った。読むなら今が最後と思って、実家で茶色くなっていた本を取ってきた。しかし、次々に新発見が続いている免疫学の世界。さすがに古すぎるのではないか。しかし、杞憂だった。名著は後世に残る良い例なのだろう。現にこの本はいまだ新刊が↓2020/06/27
やいっち
42
30年ほど前…出版直後に読んだっけ。名著だと思う。朝日新聞にて久々多田富雄の名を目にしたので本書を思い出した。
bapaksejahtera
15
30年前の本。その後我が国研究者のノーベル賞受賞等、この学問には更に急激な進展があった。免疫学の今日を知ろうとすれば既に色褪せた所も多いのだろうが、文章家としての著者の筆力と論理構成は、その梗概を十分に知らしめる。免疫機作の複雑さと巨大システムは、単に自己と異なる異物の排除機能を超え、遺伝子配列によってアプリオリに決定されると思われがちな自己なる物は、危うくも移ろい行く物と認識させる。免疫系を担うリンパ系細胞群は体内に遍満し総量1kgに及ぶ。臓器を形成せぬ系の為スタートが遅れた学問への興味を励起する名著。2022/07/13
まると
14
名著というので積んであった本。コロナ禍の今でなければ整理できないだろうと読んだ。体のどこかが腫れたり痛かったり、風邪やばい菌などで熱を発したりした時、体を元に戻そうと必死に頑張っているのも、すべて免疫のスーパーなシステムなわけですね。その基礎知識が学べてとても勉強になった。科学史を交えて生物の不思議さをわかりやすくひもとく書き手といえば、最近では福岡伸一さんが思い浮かぶが、「生物と無生物」を問うたその新書よりも少々難解でした。まあ、自分は科学者でも医師でもないのだから、大意をつかめただけで良しとします。2020/04/15
-

- 洋書
- CORRIDA