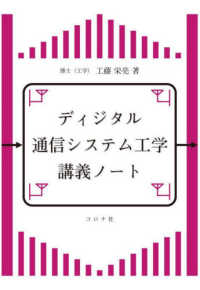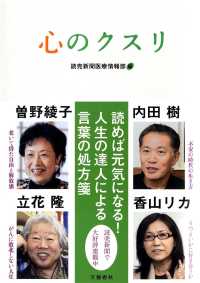目次
呪縛の意匠―過去へ行く為に
古典の時代―もう一度、歌う為に
「集団批評の精髄―あるいは全体を語る個について」
愛嬌―または幻想する肉体
怪―歌舞伎の論理
江戸の“様式”
江戸の段取り
江戸の“総論”
江戸はなぜ難解か?
明治の芳年
私の江戸ごっこ
安治と国芳―最初の詩人と最後の職人
その後の江戸―または、石川淳のいる制度
立たない源内と『痿陰隠逸伝』、そして国芳の侠気はヤクザの背中に消えて行く
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
A.T
16
江戸=江戸時代=前近代の日本を、歌舞伎、浮世絵、近世の社会システムから推測していく雑文、エッセイ集だけで一部上下段組の458ページの単行本にするなんて治ちゃんにしかできない。サブカルチャーに対するハイカルチャーに挑む舌鋒は鋭い。撫で撫でした表面的なハイカルチャーな文化論、歴史観を尻目に、ズバッと切り込む。要は、明治維新からの近代を胡散臭い、四民平等を謳う根本には市民たる町人には担えなかった現実を「江戸にフランス革命を」という皮肉に込めた一冊。未読の橋本治本を一巡したら再読、決定。2025/08/23
amanon
4
とにかく「江戸はなぜ難解か?」を読むのが辛かった(苦笑)。最初はわりに興味深く読めるのだけれど、終盤になると殆ど苦行。江戸についての細かい分析が延々と述べられると、しまいには食傷気味に。ただ、江戸のなんたるかはこの文章だけでかなりイメージがつかめるけれど。また、一般的なイメージと違って、江戸時代はそれ程遠い昔ではないということが、本書を読めばよく分かる。とりわけ江戸明治を生きた浮世絵師芳年の経歴に顕著である。それにしてもこれだけ画期的と思われる江戸論に対して、アカデミズムはどう反応したのかが気になる…2019/04/09
koheinet608
3
橋本治氏は、①江戸→明治での、 日本語の断絶、そして②敗戦→戦後 での、これまた日本語の断絶を 深く理解し、その断絶を繋げるような仕事をした。この著作もそう。 現代日本人の 「歴史(過去)に繋がっていないデタラメな感覚」を非常に危惧したんだろうと思う。 また、破滅するような「選択≒自滅」をするっていう確信があって、「もう次はないよ」という実感があったんだと思う。氏は、ひたすら優しい。 『桃尻娘』から古典の現代語訳 まで、多くの作品を残した。 ほんと、惜しい人が、もういない。 2023/10/14
iwasabi47
2
近代は野暮といいながらも、近代=野暮=啓蒙の人だとおもう。そして胸先三寸に突きつける。『てめえはどうなんだい』2021/10/14
かにこっこ
1
井上安治の絵、いいですね…まだ自分の絵を掴みあぐねているユトリロといった趣。んでオチは源内のアレかい。町人文化から革命が生まれる余地はない(なぜなら江戸の文化は思想からではなく様式からはじまるからだ)からこそ、江戸は近代へ続いてはいかなかった。まあ橋本治がひたすら近代嫌いなことはわかりました。町人文化、社会政治に実に無責任であるところとか、最近のオタクカルチャーとかなり親和性がある気がしますが。2020/04/27