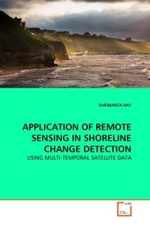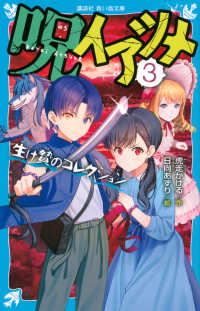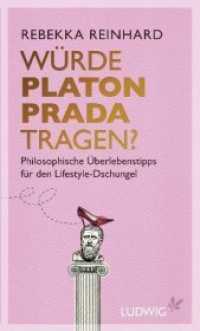出版社内容情報
「障老病異」を抱え、人びとがともに生きて在ることを思考してきた社会学者・立岩真也。「生存学」を基盤とする、アカデミアと当事者、支援者が手に手を取り合う基盤はどのようにつくられ発展していったのか。『生の技法』や『私的所有論』に始まる立岩自身の、また立岩との協働によって練り上げられた仕事を総括し、またそのバトンを引き継ぐための総特集。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
モルテン
7
立岩先生の追悼特集。気が付くと、命日も過ぎていた。書いている方のほとんど全てが立岩先生のその独特の文章について触れている。そういう私も、あの文章が好きだ。2024/08/11
バーニング
4
稲葉振一郎や村上潔らによる立岩真也の議論に対する批評も含まれるが、多くは立岩の共同研究者や立岩が立命館で育てた研究者たちによる追悼文集といった構成。立岩自身が『現代思想』で何度も連載を持っていたという縁も影響しているだろうが、一冊丸ごとこういった構成は珍しいなと思いながら読んでいた。なぜ彼の死を関係者が悼むのか、残された仕事や課題にどう向き合うべきなのか。生きること、というシンプルで複雑な事象に対していろいろな事を考えながら読んだ一冊だった。2024/11/06
YASU
3
さいきんはもっぱら図書館で借りてばかりなのだが、こればかりはアマゾンで予約して手に入れた。けっか大正解!コストパフォーマンス抜群!大澤真幸と稲葉振一郎だけでも十分!いや、他の方々もみな思い入れを込めて書いている。2024/02/09