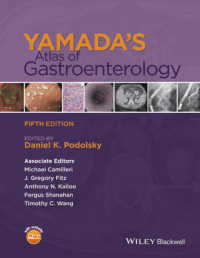内容説明
スリッパの使い分けに戸惑ったり、うわっ、このスリッパ、トイレのやつやん…!日本人に「無宗教なんです」と言われて驚いたり、えっ?無宗教ってどういうこと…?「花見」が夜に開催されたり、いや、暗くて桜、見えへんやん…!マリ出身。大学学長。日本に住んで、30年。
目次
序章 空気読めない―暗号の国
1章 無宗教―「いただきます」って、宗教やん
2章 住宅―日本はスリッパ多すぎる!
3章 おもてなし―逆にこっちが、疲れるし
4章 花見―暗くて桜、見えへんやん!
5章 マナー―まわり見えてない行列やな
6章 観光地―この場所、矛盾だらけやで
7章 外人―マリにハロウィン、ないねんけど
8章 日本人―朝ごはんから、全体主義?
終章 空気を読む―共生の知恵
著者等紹介
サコ,ウスビ[サコ,ウスビ] [Sacko,Oussouby]
京都精華大学教授・学長。1966年、マリ共和国生まれ。高校卒業後、国費留学生として中国に留学。1991年、来日。京都大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程修了。博士(工学)。2002年、日本国籍取得。専門は空間人類学。「世界の居住空間」「京都の町家再生」「コミュニティ再生」「西アフリカの世界文化遺産の保存・改修」など、人間・社会と建築空間の関係性を調査研究している。バンバラ語、マリンケ語、ソニンケ語、英語、フランス語、中国語、関西弁をあやつるマルチリンガル(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
111
昨年の「サコ学長、日本を語る」の衝撃に較べて、「なんでやねん」のインパクトが薄い気はするが、それでも、日本社会の「空気」や「マナー」に対するサコ学長の指摘は傾聴に値する。「空気を読む」のは他者への配慮から生まれた工夫なのに、「空気」が無自覚的に他者を排除し内側に逃げ込むために利用され、これが「公共性の喪失」に繋がっていると言う。更に、マナーとは、そもそも他者への気遣いや共生の作法なのに、日本では、マナーの出発点が「他人の目」にあると指摘。日本を知り尽くし、日本を愛するサコ学長の言葉だけに、重く響く。2021/12/20
夜長月🌙
61
サコさんはアフリカのマリ共和国出身で今では京都の大学の学長です。かつてはKYでしたが今では「空気を読んだ」上での日本の「なんでやねん」をいくつも取り上げています。一例ですが「にぎやかでよろしますね」の翻訳は難しいでしょう。2025/08/07
りょうみや
26
著者の本は初。マリ出身大学学長の日本文化論。サクッと読めるが奥が深い。言い換えるなら空気論の内容。日本の良いところも多く述べているが批判の方が手厳しい。日本人の「空気を読む」は協調性を超えて「逃げ」「問題の先送り」、物言わぬ文化は日本人同士でしか成り立たず、多様化する社会においては脆弱など。文中に所々挿入されている関西弁でのツッコミが的確でおもしろい。2022/02/10
Speyside
23
日本人が「空気を読む」のは協調性があるからなのだと、よくいわれます。しかし私は、その場で本音を伝えない「逃げ」こそ、協調性がない行為だと思っています。「空気を読む」「はっきり意見を言わない」「みんなとは反対の意思を悟られまいとする」など、日本では美徳と思われがちな行為は、むしろ人間関係を冷淡にしているように思います。<中略>もともと「空気を読む」というのは、相手に対する配慮だったはずです。わかりあうことをあきらめて、人を避けたり、問題を先のばしにしたりすることが、「空気を読む」ことだといえるのでしょうか。2022/09/18
ジャズクラ本
21
◎日本に30年間滞在し日本国籍を取得した、マリ共和国出身で京都精華大学学長である著者が見た日本の不思議のあれこれ。言われてみれば我々には当然と思われるヘンテコなことが軽い筆調でそこここに。時折差し挟まれるツッコミに笑いつつ、そりゃあ、外人さん戸惑うわなあ。。そんな表面的なあれこれが、読み進めていくうちに物事の核心に迫る奥の深い日本論になっていく。サスガ、、海外出身ながら伊達に日本の学長さんを務めてません。なまじな日本人よりも日本を知るマリ出身の日本人による一冊でした。2021/12/06
-
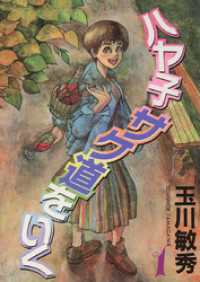
- 電子書籍
- ハヤ子サケ道をいく(1)
-
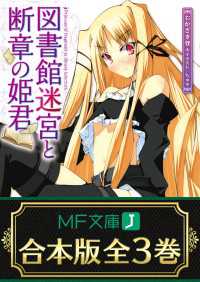
- 電子書籍
- 【合本版】図書館迷宮と断章の姫君 全3…