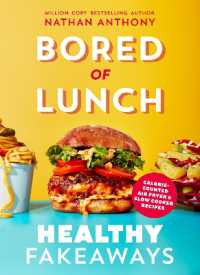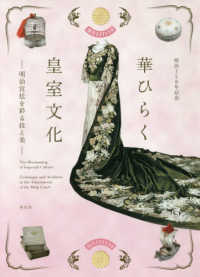内容説明
ロボット神話を解体する!ポストプルーラル人類学の挑戦。マンガやアニメのなかで活躍する一方、人間の生活を支える新技術として研究されるロボット。私たちはなぜ彼らを生み出してきた ?ロボットをめぐる文化/科学的実践を分析し、機械と生命、欧米と日本、過去と未来をつなぐ機械人間と日本人の密やかな関係を描き出す。
目次
第1章 あいまいな日本のロボット
第2章 はじまりのロボット
第3章 文化としてのロボット
第4章 科学としてのロボット
第5章 ロボットの時間
第6章 私たちとロボット
著者等紹介
久保明教[クボアキノリ]
1978年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間科学)。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所研究員を経て、現在、一橋大学大学院社会学研究科専任講師。専門は文化人類学、科学技術の人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
14
ロボットの曖昧さは境界性からくる。人間/機械、伝統/科学、日本/欧米、過去/未来等、様々な二項対立を線引きし接続し折りたたみ変容させるのは、ロボットの曖昧さだ。搭乗型の巨大ロボットはビジュアル的にも、人と機械が相互包摂の入れ子状態になる様が描かれる。日本人の曖昧な微笑みとロボットの持つ曖昧さとの親和性は、サブカルチャーやB級感こそがメインカルチャーであるこの国を象徴しているかのように見える。本書によればロボットとは定義できない存在だという。2021/11/25
いまにえる
0
「ロボット」は実は自明な存在ではなく社会・文化的なものである。その神話の外に身を置き、その神話を捉えようとする試みである。特に人間と環境を調和させる媒体としての機械がロボットである(べきだ)という考えはなるほどなと思った。ロボットを通じて私たちを問い直すと書いてあったが、それはロボットについての価値観から我々の自然や機械に対しての価値観を図る、人間とロボットの類似性から人間独特のものは何か考え直すといったことだと解釈した。2017/11/09
☆☆☆☆☆☆☆
0
ストラザーンmeetsロボット(&アニメ漫画)。全体を通して濃密かつ卓抜な分析で、AIBOをめぐる時間性について論じられた第5章は感動的ですらあります。ただ、もう少し民族誌的な記述も読んでみたかった気はする。2016/01/02
-
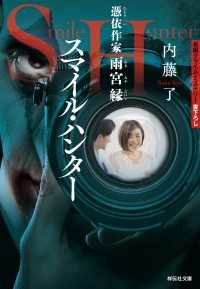
- 電子書籍
- スマイル・ハンター 憑依作家 雨宮縁 …