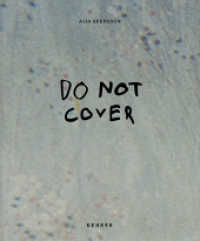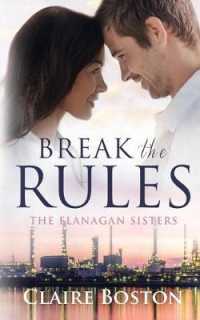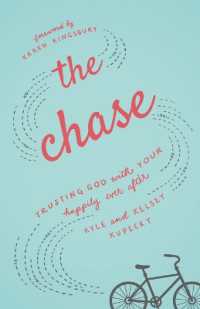内容説明
「3・11」大震災は哲学に何を突きつけたか。大震災は、日本に張りめぐらされた権力構成体=「原発ペンタゴン」を明るみに出したが、これを機に哲学が問うべきは、近代において理性が、技術・テクノロジーに依存する「技術的理性」に変貌したという事実である。本書は、原発をはじめとする技術問題を俎上に載せて「技術的理性」の諸特質について論じ、その変革可能性を考察する。
目次
第1章 技術的理性とは何か(目的と適合性―技術的理性は目的に対する手段の発見に関心をもつ;自然の支配―制御可能性への過信;人間の支配―人間に対する無関心 ほか)
第2章 「3・11」原発事故と技術的理性(電気エネルギーの獲得と原発採用―技術的理性と原発ペンタゴン;自然現象の予測・制御可能性への過信―技術的理性は放射性物質の核分裂過程さえ制御可能と見る;津波と被害予想の軽視―「科学的データ」への不当な固執 ほか)
第3章 「3・11」後の技術―技術的理性を超えて(技術使用の正義論―人格主義的正義原理;いかにして技術的理性は変革しうるのか)
著者等紹介
杉田聡[スギタサトシ]
1953年埼玉県に生まれる。1984年北海道大学大学院文学研究科博士後期課程(哲学専攻)単位修得満期退学。1984年北海道大学文学部(哲学科倫理学講座)助手、’87年、帯広畜産大学講師、’89年、同助教授を経て、帯広畜産大学教授(哲学・思想史)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mealla0v0
2
「3・11」――福島原子力発電所事故に至らせたのは、具体的には東電の無策無能ゆえにだが、その背後には「技術的理性」が控えていたのだ。これを打破しないことには、われわれは「3・11」後には行くことができない――というようなことが書かれているのだが。アドルノ=ホルクハイマーの言う「道具的理性」のヴァリアントとしての「技術的理性」という切り口や、そうやって分析された内容は常識的に頷ける部分があるものの、非常にナイーヴな議論となっており、規範性に欠ける。2017/09/27
アルゴス
1
著者の技術的理性批判は明確であり、きちんて提示されている。この書で列挙されている七つの特徴は、どれもまっとうなものである。またこうした技術的な理性の産物として、原発と自動車があげられているのも、よく理解できる。批判の筆がときにアジテーションのような雰囲気になるのは、少し失敗ではないか。もちろん原発と自動車が現代の日本の最重要のリスク要因であることについては、著者とまったく同感である。 ★★★☆2017/11/14
-

- 和書
- 生命と自由を守る医療政策