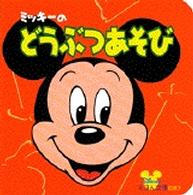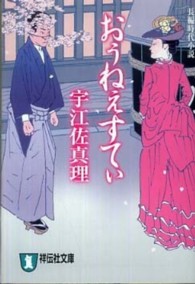内容説明
親たちの育児戦略の変化、育児言説の生成・伝達のプロセスを通して、育児という日常的営みに潜む、かくれた権力関係を解きほぐす。
目次
序章 育児知識と育児戦略―分析の理論的枠組み
第1章 育児メディアの変遷と「母」の再生産
第2章 資源としての育児雑誌―育児雑誌の分析から
第3章 育児言説の歴史的変容―『育児雑誌』から『ベビーエイジ』へ
第4章 「子ども中心主義」のパラドックス―「共感型」育児雑誌の興隆
第5章 少子化時代の育児戦略とジェンダー
第6章 子育てネットワークと母親たちのライフストーリー
第7章 戦略としてのヴォイスとその可能性―父親の育児参加をめぐって
第8章 育児知識の生成・伝達・受容
著者等紹介
天童睦子[テンドウムツコ]
1957年生まれ。東京女子大学大学院文学研究科修士課程修了(社会学専攻)。早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。現在、名城大学人間学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
14
2004年刊。バジル・バーンスティンの言説理論を参考にしながら、育児雑誌の言説分析を行った、社会学の研究書。古くは大正時代に編まれた育児雑誌の分析から始まり、俸給生活者が多い都市の新中間層を読者対象としたのが育児雑誌であったとする。すなわち教育による業績達成に関心が高い階層を中心に育児雑誌が受容されていった。ただ、戦前から戦後まで一貫しているのは、雑誌の言説が母親を育児のエージェントと規定しているところだという。つまり子育ては女性の役割というジェンダー規範を強化するのが言説の効果だという。難解だった。2024/08/23
ふじか
1
育児雑誌の、と付いていたのでここ最近のクー○ンの反ワクチンを推奨するような記事など、ああいう悪い意味での育児雑誌の尖鋭化の話があるかな?と思いつつ手に取ったので、そういう意味では求めた内容ではなかったかな……。 しかし、この本が出た2004年から15年が経過して変わった部分も未だ変わらない部分も色々あるな、と感じる部分と、それよりも以前の時代の育児雑誌の特集から見る子育ての姿も垣間見えてとても面白かった。2019/04/03
-

- 和書
- やさしいドイツ語入門