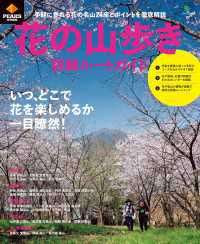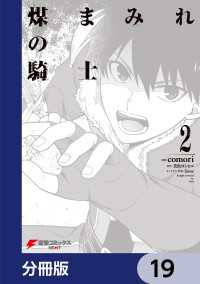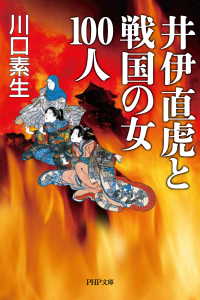内容説明
テレビ番組を超え、さまざまなメディアに浸透するクイズ形式の文化―その歴史的・社会的変容と国際的な移動をあきらかにする。
目次
序章 「クイズ文化の社会学」の前提
第1章 日本のテレビクイズ番組史
第2章 クイズと審問―五〇年代アメリカのクイズ・スキャンダルについて
第3章 クイズ番組の誕生
第4章 クイズ番組の精神分析
第5章 メディア的「現実」の多重生成、その現在形―クイズ形式からの観察
第6章 「お茶の間」という空間―クイズ番組と一家団らん
第7章 いつかハワイにたどり着くまで―海外旅行の“夢”の行方
著者等紹介
石田佐恵子[イシタサエコ]
1962年栃木県生まれ。1998年博士(社会学)。現在、大阪市立大学大学院文学研究科助教授。専攻は現代文化研究、知識社会学
小川博司[オガワヒロシ]
1952年東京都生まれ。1979年社会学修士。現在、関西大学社会学部教授。専攻はメディア文化論、音楽社会学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
レミニサンス
27
小さな頃、母親が家の仕事に忙しくて、テレビでも見ていなさいと言われたので、物心ついた頃からテレビを見ていました。テレビで字を覚えたね!と言われるぐらい見ていましたが、クイズ番組をよく見て勉強していました。クイズを題材に社会学者の方々が様々に分析された本です。クイズというより、クイズ文化、という視点。カルチュアル・リテラシー~継承されるべき文化を理解する能力、がクイズの設問となり、クイズはとっつきやすい文化の教科書であり常識の事典として機能する。~14ページの文章を雑だけど要約。2023/01/04
nbhd
24
ふだんテレビのニュースをつくる仕事をしたりしていて、「ぶっちゃけ、VTR原稿の書き方って、だいたいクイズとおんなじなんだよねぇ」ってことには、薄々気づいている。で、その点を鋭く抉って分析した論文「メディア的『現実』の多重生成、その現在形」(遠藤知巳)を読んだ。「このあと、〇〇が口にした衝撃の言葉とは⁉」「3位は星野源、2位は菅田将暉、では1位は?」など、テレビに蔓延するクイズ形式について、かなりややこしく書かれているけど、ニュース当事者にとっては本質的な記述に満ちている。これ、めちゃすごい。2022/01/03
つまみ食い
5
日本に「クイズ」なるジャンルが登場し、根付く(「茶の間」といったたぶんにフィクショナルな空間を経由たりしながら)過程やになってきた機能などを論じるアンソロジー。視聴者は何を享受するためにクイズ番組を視聴しているのかを心理学的に論じた山本論文が特に個人としては興味深かった。2022/03/20