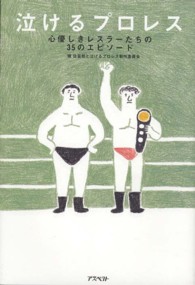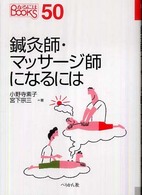内容説明
1900年(明治33)生まれ。五つの年から寄席にでて話芸ひとすじに生き抜いてきた根っからの寄席芸人、六代目・三遊亭円生の語る素噺一代記。
目次
明治篇(出生;幼時;上京;寄席出演 ほか)
大正篇(名人円喬;噺家の服装;柳橋の円橘;楽屋奇人伝 ほか)
昭和篇(青山三光亭;引越し時代;柳家三語楼;第二次研究会 ほか)
芸談篇(自分の芸;芸の行儀;芸の味;芸の基本 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
tama
10
図書館本 圓生さんファン(落語で) 明治、大正、昭和戦前・戦後に分け、身の回りのことや芸のことを。大阪生まれって全然知らなかった!4歳で上京。明治の章で、時計の話。あてにならなかったそうで。「あたしの時計はいい時計でね。進むからね」。大正の頃新宿3丁目の末広の近所に住んでいて、狸囃子が聴こえたことがある。「あたくしども」「あたしゃァ」「「出来やァしない」「これやァ」「でげしょう」「まずいてえのか」「言やァがって」「まァようがしょう」書き言葉含めて江戸言葉が柔らかいのに感動! 2020/07/27
犬養三千代
9
明治から昭和までの寄席にまつわる圓生師匠が体験した様々なことがらが描かれている。知らない落語家さんのオンパレードだが、しみじみと感じられた。手元に置きたい一冊。これを手ががりに各各の落語家さんを見ていきたい。2023/08/22
Gen Kato
3
再読。折に触れて読み返したくなるのは、内容も然りだけど、圓生師の語り口がいいからですね。掲載写真も明治~大正期のものとは思えぬほどクリアです。2013/08/09
ymkk2
2
古典と新作それぞれの役割だとか、しきたりやルールは理由があって継がれているものだとか、そんなことを考えました。2016/04/03
DEN2RO
1
昭和落語界の名人が明治33年の出生から昭和40年に至る半生を語った本です。高座の語り口を髣髴とさせる、軽妙で端正で洒脱な口調で、大震災と二度の大戦を挟む波乱に富んだ66年間の寄席人生を詳らかに語っています。2年近い苦しい満州生活の後、芸が格段に進歩した一節は圧巻です。2009/02/28