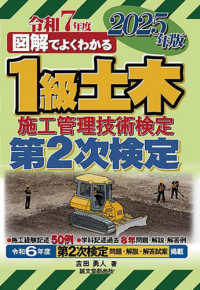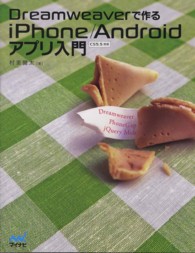内容説明
本書は、三十一篇の短編、総計二十万語、一九三九年から一九七七年にいたるあいだに書かれた著者のロボットものの作品を集めたものである。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
tama
7
図書館本 存在を知らず、物色していて発見。ロボット三原則にまつわる短編(またはショートショート)で構成。やたら重くて腕が疲れた。飛ばし読みしたくなるところもあったが結局みっちり読めた。これ自体が「ロボット生物学・ロボット史」と呼べるような配列になっていて、最後の作品に出てくるようなロボットなら「ロボットみたいなやつ」と言われるのは非常に光栄なことと思う。2013/10/17
roughfractus02
5
『われはロボット』『ロボットの時代』と他の未収録のロボット短編を集めた完全版(実は不完全)だが、作者がどんなタイプ別にロボットを造形し、それらと人間はどう関わり、その進化に伴って社会はどんな問題に直面するのかが7部構成で通覧可能だ。自動運転車への思い(「サリーはわが恋人」)、数も文字も不要なIoT世界(「いつの日か」)、コンピュータ依存社会で誤りを犯すコンピュータ(「もしマルチヴァックが正しいなら・・・」)、ロボット側が捉えた生命の定義(「二百周年を迎えた人間」)等、読者にも身近な機械との未来が描かれる。2018/11/26
古宮
5
どの話も憂慮と期待に心動かされて面白かったです。個人的に「ミラー・イメージ」に特別心惹かれて、R・ダニール(ロボット)がイライジャ(人間)のことを親しみを込めて…というと違和感があるけれど、『フレンド・イライジャ』と呼ぶ事やダニールは自分の困った際イライジャに助けを求める事、つまりダニールがイライジャに対し人間への主従関係でありながら同時に友情を思わせる様な行動を取る事、そしてイライジャはそれを許容している、その信頼の様な関係性に憧れを思って良い作品だなぁと思いました。2017/01/07
longscale
4
ロボット工学三原則は、作動範囲を律する「行動」原則になっている。ロボットは基本的に「◯◯をしろ」と命令=指示される存在であるにもかかわらず、その是非を改めて自ら「判断」しなければならない。本来あるべき設計思想としてはたぶん、「やってはならない行動=無効な命令」の一つひとつを具体的に制限すべきなのに、著者のロマンチシズムはそれを許さない。「行動」を禁じる一方で、求めているのはあくまでも「判断」であるという矛盾……。知能というよりも、それはもう倫理なんだと思う。一気に読むにはさすがに分厚かったが、面白かった。2016/11/27
ALBA
4
重量1.1Kgの本を通勤の行き帰りで読むのは大変で時間もかかりましたが、それだけの満足感はありました。 ”スーザン・キャルヴィン”シリーズのようにちょっと難しいD題材もありましたが、だいたい楽しく読める作品ばかり。 映画「アンドリューNDR114」が大好きなわたしとしては「二百周年を迎えた人間」は感動的でありました。2013/07/27
-

- 和書
- 会計認識領域拡大の論理
-

- 和書
- 哲学夜話 鶏鳴双書 17