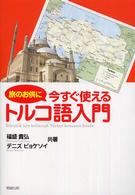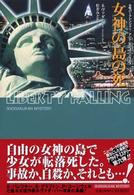出版社内容情報
日本は「大復興」する中国と「アジア回帰」する米国との狭間に位置する「境界国家」である。
その戦略は、明治以来の「アジアか欧米か」という二者択一ではなく、
日米同盟と日中協商を共に追求する二者両立でなければならない。
それは「境界国家」日本にとっての
「究極の選択」であり、「外交の真髄」でもある。
【主な目次】
はじめに
序 章 「境界国家」日本の選択
1 漂流する日本丸
2 国家の盛衰
3 「責任ある大国」への期待
4 「第3の危機」にある日本の選択
第1章 チャイナ・ジレンマ――強大化する中国の衝撃
1 中国「大復興」のチャンスとリスク
2 「大復興」する中国の対外姿勢
3 軍事パワーのせめぎ合い
4 政治経済モデルと価値をめぐる相克
第2章 激動するアジア秩序の形成――日本のアジア外交の回顧と展望
1 日本の「アジア重視」
2 地域主義の胎動
3 地域主義の深化と拡大
4 パワーと理念――日米同盟と東アジア秩序
5 「東アジア共同体」の行方
6 米中関係の新展開
7 自由で繁栄するアジア太平洋秩序の形成
第3章
内容説明
日本は「大復興」する中国と「アジア回帰」する米国との狭間に位置する「境界国家」である。その戦略は、明治以来の「アジアか欧米か」という二者択一ではなく、日米同盟と日中協商を共に追求する二者両立でなければならない。それは「境界国家」日本にとっての「究極の選択」であり、「外交の真髄」でもある。
目次
序章 「境界国家」日本の選択(漂流する日本丸;国家の盛衰 ほか)
第1章 チャイナ・ジレンマ―強大化する中国の衝撃(中国「大復興」のチャンスとリスク;「大復興」する中国の対外姿勢 ほか)
第2章 激動するアジア秩序の形成―日本のアジア外交の回顧と展望(日本の「アジア重視」;地域主義の胎動 ほか)
第3章 日本最後の「開国」―「奥田ミッション」が残したもの(日本の再生とアジアへの「開国」;「アジア経済再生ミッション」(「奥田ミッション」) ほか)
終章 「境界国家」日本の再生(もう一度「開かれた」をキーワードに!;日本の強さとアジアの「ハブ国家」 ほか)
著者等紹介
小原雅博[コハラマサヒロ]
1980年外務省入省。アジア局地域政策課長、経済協力局無償資金協力課長、アジア大洋州局審議官などを務め、現在は在シドニー総領事。海外は北京、香港、NY(国連代表部)、ロサンゼルスに勤務。東京大学卒、UCバークレーで修士号を取得し、立命館大学より博士号(「国際関係学」)を授与される。早稲田大学や立命館アジア太平洋大学で客員教授も務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。