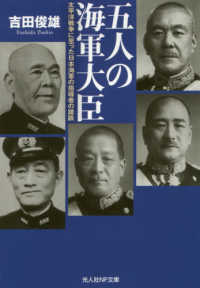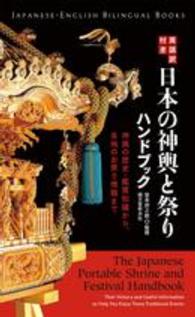内容説明
19世紀初頭のフランスで、なぜ、ひとりの浮浪児が突然、「野生児」として脚光を浴び、今日にまで影響を与えたのか。自閉症や言語習得の臨界期という現代の問題の原点といえる「野生児」。その実像は、本や映画で世界に広まったものとはまったく異なっていた。人間科学の勃興、中央と地方、ナポレオンの皇帝即位…学問、社会、政治の交錯から浮かび上がる、「アヴェロンの野生児」の事実とは?
目次
序章
1章 アヴェロン県、ロデス中央学校
2章 パリ、国立聾唖学校
3章 イタールの教育と挫折
4章 舞台裏―人間観察家協会と内務大臣
5章 禁断の実験
終章
著者等紹介
鈴木光太郎[スズキコウタロウ]
東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。元新潟大学教授。専門は実験心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
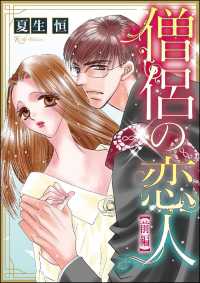
- 電子書籍
- 僧侶の恋人(単話版) 【前編】