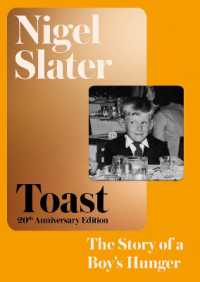出版社内容情報
米軍の戦車による介入までも招き、「来なかったのは軍艦だけ」として知られる東宝争議。戦後日本映画黎明期の労働争議は、多くの共産党員が所属していたことからも、レッドパージの先取りをなすものといわれてきました。しかし東宝には党員でない多くの映画人たちがおり、彼らもまた争議の第一線にたち、最後まで運動を担ったのでした。黒澤明、成瀬巳喜男、衣笠貞之助、五所平之助ら日本を代表する映画人たちは、何を求めて苛烈な運動の現場にとどまり続けたのか、東宝とはいったいどのような場であったのか。会社・組合の内部資料、当事者たちの日記や証言など、貴重な一次資料を駆使して、芸術と興行的価値の対立をめぐる争議の実像を生き生きと再現します。
この研究は、一九四六年から一九四八年にかけて東宝株式会社で発生した三次にわたる労働争議を対象として、労使の主張によって構成される争点を中心にその実体を明らかにすることを企図している。このことを通して、映画という文化生産における経済と芸術の対立・相克の内実を明らかにすること、これが本書の目的である。・・・・・・経済と文化という各々固有の律動原理をもつ社会動力が、映画という文化生産の場において、労働争議を媒介に交錯・拮抗する相の実態を、戦後直後の時代背景のうちに描き出そうとする本書の試みは、誤解をおそれずにいえば、映画の芸術的価値の解明である作品分析やそれを生み出した演出家の映画思想・映画文法の解読である作家論によって多くを占められてきた既存の映画研究に対して、映画の文化社会学的・文化経済学的アプローチをなすものとして位置づけることができよう。(「序章」より)
-----------------------------------------------------
【新 刊】
『 資本主義黒書 市場経済との訣別 』 R・クルツ著 (上巻6930円 下巻4620円 2007)
内容説明
戦車まで出動した争議の内実は?「来なかったのは軍艦だけ」として知られる東宝の大労働争議。「創造の自由」を求めて困難な争議を生きた映画人たちの闘いを、当事者の日記や組合内部文書、会社のマル秘資料などに丹念にあたって、はじめて実証的に跡づける。「解放の記憶」をきざむ争議像の再構築。
目次
序章 課題と方法―なぜ東宝争議なのか
第1章 第一次争議
第2章 第二次争議
第3章 組合規制
第4章 経営危機
第5章 第三次争議
終章 結論―東宝争議とは何であったのか
著者等紹介
井上雅雄[イノウエマサオ]
1945年北海道生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。佐賀大学、新潟大学を経て、立教大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
富士さん