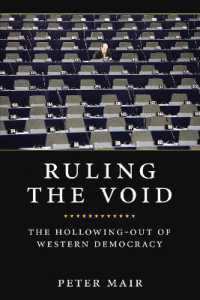出版社内容情報
本書で著者は、さらに新しい次元に飛び出そうとしています。「オートポイエーシスの第四領域」では、その脱出を、体験的レベルの事象を扱うのに適したシステム論と現象学を援用して行なおうというのです。身体療法、認知運動療法などに携わることで得られた新しい思考を、それにふさわしいみずみずしい文体で展開します。リハビリやスポーツのトレーニングの実例も豊富で説得的です。
最先端のシステムの機構を解明しようとするオートポイエーシスは、当初より現象学に近いところにいた。それはこのシステムの機構が、知ではなく行為というレベルで設定されているからである。ヴァレラもルーマンも、異なった仕方で現象学と内的な関連を図ろうとしている。本書でも、システムと現象学の内的で有効な回路を探り当てようとしている。そして数々の問題を扱うことになった。……本書全体で狙っているのは、どのようにして体験レベルの経験を形成するかであり、それにかかわる基本的な働きを「注意(アテンション))」と「気づき(アウェアネス)」に限定していることである。注意は、現実がそれとして成立する働きであり、気づきは、知るということ以上に行為の調整を担っている。いつものように哲学としても、経験科学としても、そして制作としても、果敢に踏み出していきたいと思う。(「はじめに」より)
------------------------------------------------------------------------
【関連書籍】
『 自閉症 』 藤居学著 (定価1890円 2007)
『 私の身体は頭がいい 』 内田樹著 (定価1890円 2003)
『 アフォーダンスの心理学 』 E・S・リード著 (定価5040円 2000)
【新 刊】
『 人間改造論 』 町田宗鳳・島薗進編 (定価1890円 2007.9月)
内容説明
行為の継続を通して自己を形成してゆくオートポイエーシスの思想。眼で見て頭で考える西欧の知の行きづまりを、身体知と行為知にもとづくこの斬新な思想とシステム現象学によって乗り越え、セラピー、リハビリ、トレーニングなどの実践の現場にまで新境域を拓く。
目次
1 システム現象学とは何か
2 認知行為システム
3 身体システム
4 人間再生プログラム
5 情動・感情のシステム
6 オートポイエーシスの第四領域
終章 ミケランジェロの決断
著者等紹介
河本英夫[カワモトヒデオ]
1953年、鳥取県生まれ。1982年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。1996年、東洋大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
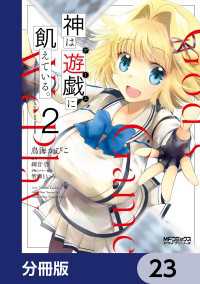
- 電子書籍
- 神は遊戯に飢えている。【分冊版】 23…

![入門ロシア語の教科書 [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48761/4876153973.jpg)